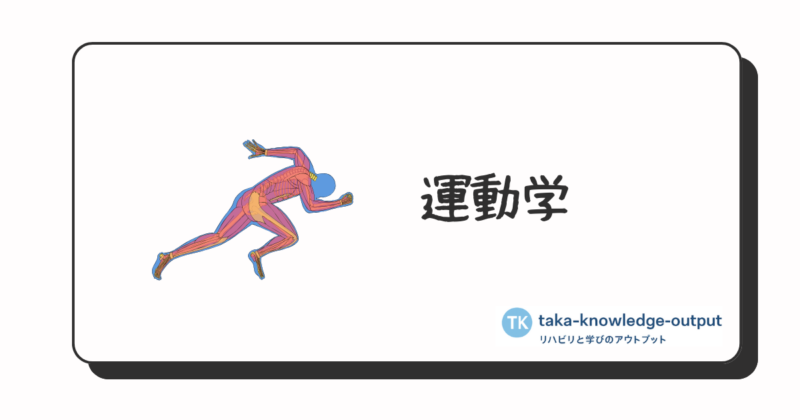痛みを伝える神経の種類と侵害受容性疼痛のメカニズム:臨床に役立つ基礎知識

痛みを理解する第一歩は「神経」から
リハビリテーションにおいて患者が訴える最も一般的な症状は「痛み」です。その治療や説明を的確に行うためには、痛みがどのように発生し、どのルートで伝達されるのかを理解しておく必要があります。
痛みを伝えるのは末梢神経の中でも感覚神経です。その末端には多様な受容器が存在し、中でも「侵害受容器」が痛みを感知します。ここから痛みの伝達が始まります。
侵害受容性疼痛のメカニズム
侵害受容器が刺激を感知すると、その信号は電気的インパルスに変換され、神経線維を通じて脊髄へ送られます。
- 運動神経・自律神経 → 脊髄前角を経由
- 感覚神経 → 脊髄後角を経由
この違いが重要です。感覚神経の信号は脊髄後角に入力され、その後脊髄を上行して視床に集約されます。最終的には以下の2つの領域に投射されます。
- 大脳皮質感覚野 → 痛みの部位や強度を認識
- 大脳辺縁系 → 痛みに伴う「不快感」を認識
つまり、痛みは単なる感覚ではなく、感情的・認知的な要素も同時に伴う現象であることがわかります。
痛みを伝える神経線維の種類
末梢神経線維は大きく6種類に分類されますが、痛みの伝達に関与するのはAδ線維とC線維の2種類です。
- Aδ線維
- 一次痛を伝える
- 鋭く、刺すような痛み
- 伝達速度が速い
- 危険な刺激を瞬間的に知らせる役割
- C線維
- 二次痛を伝える
- 鈍くズキズキする痛み
- 伝達速度が遅い
- 数秒遅れてじわじわ感じる痛み
👉 臨床例
鋭い針で刺されたとき、まず「チクリ」と鋭い痛み(Aδ線維)が走り、その後に「ズキズキ」と持続する痛み(C線維)が出現します。この二段階の痛みが患者の訴えを理解する手がかりとなります。
侵害受容器の種類と役割
侵害受容器には以下の2種類があります。
- 高閾値侵害受容器
- Aδ線維と一部のC線維に接続
- 物理的刺激や高熱刺激に反応
- 危険度の高い刺激を瞬時に伝える
- ポリモーダル受容器
- C線維に接続
- 物理的刺激・熱刺激・冷刺激・化学的刺激に反応
- 刺激を数秒かけて伝えるため、危険度の低い刺激に対応
👉 イメージ
熱めのお風呂に足を入れたとき、数秒後に「熱い」と感じるのはポリモーダル受容器(C線維)の反応によるものです。
神経線維の分類方法
神経線維は大きく 「文字分類(Aα・Aβ・Aδ・Cなど)」 と 「数字分類(Ⅰa・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳなど)」 の2つの方式で分類されます。
- 文字分類 → 皮膚や侵害受容に関連する線維に多用
- 数字分類 → 筋肉や関節感覚を伝える線維に多用
臨床現場では、感覚評価や疼痛メカニズムを説明する際に「文字分類(Aδ・C)」を理解しておくと有用です。
臨床での活用ポイント
セラピストが神経線維や受容器の知識を理解しておくことは、以下の点で役立ちます。
- 疼痛の性質を説明できる
患者に「ズキズキする痛み」と「鋭い痛み」の違いを説明でき、安心感を与えられます。 - 病態の推定に役立つ
神経障害性疼痛か、侵害受容性疼痛かを鑑別する際のヒントになります。 - 治療戦略に結びつく
急性期の鋭い痛みには保護的対応が必要であり、慢性期の持続痛では心理社会的要因への配慮が重要です。
まとめ
- 痛みは感覚神経が伝達し、脊髄後角→視床→大脳皮質・辺縁系へと伝わる
- Aδ線維は一次痛(鋭い痛み)、C線維は二次痛(鈍い持続痛)を伝える
- 侵害受容器には「高閾値侵害受容器」と「ポリモーダル受容器」があり、それぞれ役割が異なる
- 知識を活用することで、臨床評価・患者説明・治療戦略に具体的に役立てられる
痛みの仕組みを理解することは、単なる知識の蓄積ではなく、臨床現場での評価精度や患者教育の質を高めるうえで欠かせません。