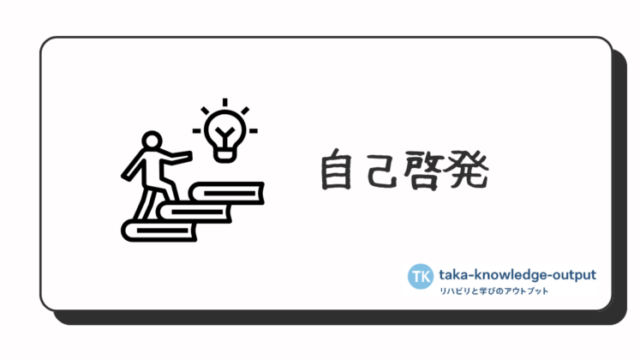愛する息子を失ってフランクリンが学んだ──感情ではなく理性で決断する勇気
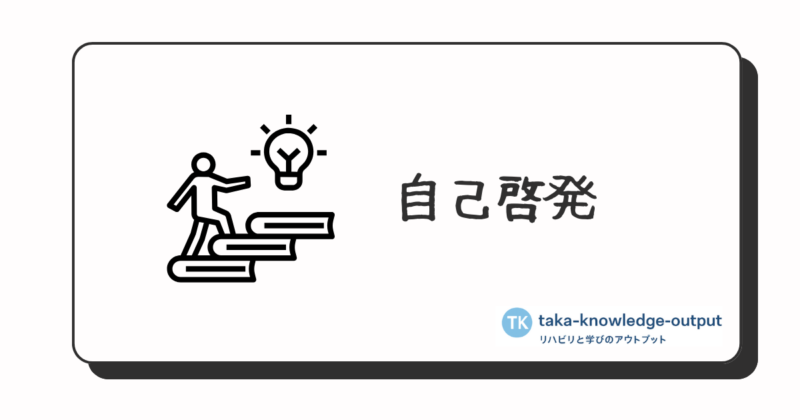
1736年、ベンジャミン・フランクリンは最愛の息子フランシス(4歳)を天然痘で亡くしました。
それは彼の人生でもっとも痛ましい出来事の一つでした。
フランクリンはその悲劇を、ただの個人的な喪失として終わらせませんでした。
彼は冷静に振り返り、**「なぜ自分は種痘を受けさせなかったのか」**を、理性の目で見つめ直します。
■「もし接種して死んだら…」という恐れ
当時、天然痘の流行は深刻でしたが、まだワクチン(牛痘法)は存在せず、
感染者の膿を使う“人痘法”という危険を伴う予防接種が行われていました。
種痘は感染を防ぐ効果が高い一方で、副作用や死亡のリスクもあり、
宗教的にも「神の摂理に逆らう行為」として反対する声が根強くありました。
多くの親たちは、
「接種して死んだら、悔やんでも悔やみきれない」
と考え、子どもへの接種をためらっていたのです。
フランクリンも当時、理性では賛成しながらも、
病弱だった息子に接種を見送っていました。
その結果、息子は天然痘に感染し、帰らぬ人となります。
■「悔やむなら、より安全な方を選ぶべき」
フランクリンはこの出来事を振り返り、『自伝』の中でこう記しています。
「接種してもしなくても、のちのち悔やむことはおなじなのだから、
より安全なほうを選ぶべきだ。」
この一文には、深い苦悩と、理性による勇気が込められています。
彼は、どんな選択にも後悔が伴うことを知っていました。
しかし、「感情に支配された後悔」よりも、
「理性的に考え抜いた末の後悔」のほうが、はるかに健全だと気づいたのです。
■合理的判断は、冷酷ではない
フランクリンのこの言葉を「感情を捨てた冷たい合理主義」と誤解してはいけません。
むしろそれは、「愛ゆえの理性」でした。
彼は息子を失った痛みを、
他の親が同じ悲劇を繰り返さないための**“警鐘”**として共有しました。
「私の例が示しているのは、接種してもしなくても悔やむのは同じ。
だから、理性で判断すべきだ。」
彼は「後悔をゼロにする」ことではなく、
「より多くの命を守る確率を選ぶ」ことを勧めていたのです。
■科学を信じるとは、“疑いながらも選ぶ”こと
18世紀当時、科学的な知見はまだ確立途上でした。
しかし、フランクリンは迷信や恐怖よりも「観察とデータ」を信じました。
彼の合理主義は、信じる前に考える姿勢の表れです。
彼が避雷針を発明したときも、教会からは「神の怒りを防ぐのは傲慢だ」と批判されました。
それでも彼は、人間の理性と経験を信じ、
「科学は神の摂理を理解する道」と答えたのです。
種痘に対する立場も同じでした。
不安を理由に拒絶するのではなく、リスクと恩恵を比較して判断する。
それが、フランクリンの言う「啓蒙の倫理」でした。
■「後悔しない選択」は存在しない
現代の私たちも、医療や教育、キャリアなどで難しい選択を迫られます。
どんなに慎重に決断しても、後から「別の道を選べばよかった」と思うことはあります。
フランクリンの言葉は、そんな私たちへのヒントになります。
「どちらを選んでも後悔するなら、
より理性的で、安全なほうを選べばいい。」
つまり、“後悔しないため”ではなく、“納得できるため”に考える。
これこそが、彼の合理主義の真髄です。
■まとめ:感情を否定せず、理性で導く
フランクリンが息子の死から学んだのは、
「感情と理性は対立するものではない」という真理でした。
- 感情は人を動かす力
- 理性は人を導く力
両者が揃って初めて、人は誠実に選択できる。
彼の言葉は、300年経った今も、私たちに静かに問いかけます。
「あなたの判断は、恐れからか、それとも理性からか?」