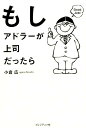『もしアドラーが上司だったら』──働く悩みを“勇気”に変える、ドラさんのアドラー流マネジメント

物語で学ぶアドラー心理学──「もし上司がアドラーだったら?」
広告代理店に勤める営業マン・リョウは、仕事でもプライベートでも行き詰まりを感じていた。同期は出世し、営業成績も伸びず、自信をなくしていく日々。
そんな彼のもとに現れた新上司・ドラさん。
アメリカの大学院でアドラー心理学を学んだという変わり者で、リョウに「命令はしない」「君たちの支援者だ」と語りかける。
本書『もしアドラーが上司だったら』(小倉広・著/プレジデント社)は、そんなドラさんとリョウのやり取りを通じて、アドラー心理学を職場にどう活かすかを描いたビジネスストーリーです。
説教くささのない会話形式で、読むほどに気持ちが軽くなる一冊です。
1. 「できていないこと」ではなく「できていること」に注目する
朝のジョギングをサボって落ち込むリョウに、ドラさんはこう言います。
「キミは週に2日も走っているじゃないか。それは“できている”ことだよ。」
アドラー心理学では、他人や自分に対して「負の注目」を向けると、勇気が失われると考えます。
逆に、「できていること」に目を向ける「正の注目」は、人を前向きにし、次の一歩を踏み出す力になります。
私たちはつい、自分の“5%の不足”ばかり見て落ち込みますが、残りの“95%の努力”に気づくことで、心が軽くなるのです。
小さな成功を認め、自分を勇気づける。
それが、アドラー流の「自己肯定感を高める第一歩」です。
2. 「やらされ仕事」なんて存在しない──仕事は“自分が選んだ”もの
仕事が山積みで疲れ切ったリョウと先輩に、ドラさんはにっこり笑って言い放ちます。
「やりたくないなら、やらなければいいじゃないか!」
最初は意味がわかりませんが、ドラさんの真意はこうです。
どんな仕事も「やる」「やらない」を決めているのは自分自身。
上司に命令されたように感じても、「やる」と決めたのは自分の意志です。
これはアドラー心理学の中心概念である「自己決定性」の考え方。
「やらされている」という思い込みを捨て、「自分で選んでいる」と気づくと、仕事の意味が一気に変わります。
「やらされているという“嘘”をやめるんだ」
この言葉は、責任を押し付けるのではなく、主体性を取り戻すための勇気づけなのです。
3. 成績や地位よりも、「人としての価値」を信じる
営業成績で同期に大きく差をつけられ、自信を失うリョウ。
「自分なんて会社にいらない」と落ち込む彼に、ドラさんは穏やかに語ります。
「ツヨシ君もリョウ君も、“人として”まったく平等だ。
成績なんて関係ない。キミは今のままで素晴らしい。」
アドラー心理学では、人の価値は「成果」や「役職」では決まりません。
人間の価値は、存在そのものにある──“機能価値”より“存在価値”が大切なのです。
売上が低くても、評価が低くても、
あなたがそこにいること自体が誰かの支えになっている。
そう思えた瞬間、人は再び前を向けるのです。
4. 上司は「命令者」ではなく「勇気づける支援者」
ドラさんは自らを「上司ではなく支援者」と呼びます。
これはまさに、アドラー心理学が説く「対等な人間関係」の実践。
上司と部下、先輩と後輩という立場の違いはあっても、
人としての価値は同じ。
相手を信頼し、尊敬し、勇気づける──これこそが本当のリーダーシップです。
命令ではなく共感で動く組織は、人が成長し、成果も自然と上がっていく。
アドラー心理学をビジネスに応用する著者・小倉広氏の狙いは、まさにこの“勇気づけるマネジメント”にあります。
5. 比べない、責めない、自分を勇気づける
ドラさんの教えの根底にあるのは、「自分も他人も責めない」という姿勢です。
比べるのをやめる。
“できない自分”を責めない。
そして、自分の選択を信じて行動する。
その積み重ねが、他人にも優しくできる心を育てます。
アドラー心理学の言葉で言えば、それは“共同体感覚”──
「自分は誰かの役に立てる存在だ」と感じることです。
まとめ:人生をシンプルにする、アドラー流の考え方
アドラーはこう言いました。
「人生が複雑なのではない。あなたが人生を複雑にしているのだ。」
私たちは「もっと頑張らなきゃ」「できない自分はダメだ」と、自分を追い詰めすぎているのかもしれません。
『もしアドラーが上司だったら』は、そんな現代人に「もっと優しく生きてもいい」と教えてくれる物語です。
仕事や人間関係に悩むすべての人へ──
“勇気づける言葉”をくれる上司・ドラさんに、一度会ってみてください。