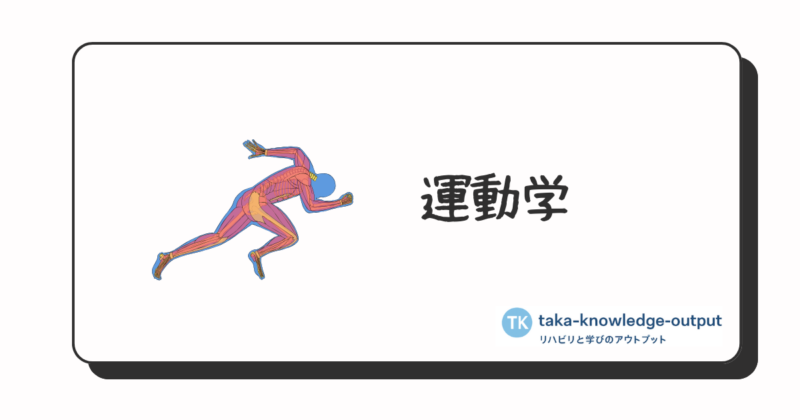膝窩筋の解剖と機能を理解する:膝外側支持機構における安定化の要

はじめに
膝窩筋は、膝後方の深層に位置する比較的小さな筋ですが、膝関節の安定性を支えるうえで非常に重要な役割を果たしています。
とくに、膝外側支持機構や下腿の回旋制御に関与することから、膝外側痛・外旋不安定症・膝窩部痛などの臨床症状と深く関わります。
本記事では、膝窩筋の解剖学的構造と機能を整理し、理学療法評価・治療における臨床的意義を解説します。
膝窩筋の解剖:位置と構造
膝窩筋は、腓腹筋の深層に位置し、
- 起始:大腿骨外側顆後面
- 停止:脛骨後面のヒラメ筋線直上
に付着します。
筋腹は短く、細い腱となって膝関節後外側を斜めに走行し、膝関節包を貫いて関節内へ進入します。
この際、腱の一部は外側側副靭帯(LCL)と交差し、その内側を通過して脛骨に到達します。
さらに、膝窩筋腱には腓骨頭と連結する膝窩腓骨靭帯(popliteo-fibular ligament)が存在し、
これは膝窩筋を介して腓骨の後方安定化に寄与する構造として機能しています。
膝外側支持機構との関係
膝外側部は、LCL・膝窩筋・外側半月板・膝窩腓骨靭帯などから構成される「膝後外側支持機構(Posterolateral Corner, PLC)」によって安定化されています。
ここで重要なのは、
- MCLと内側半月板は連結しているのに対し、
- LCLと外側半月板の間にはスペースが存在する点です。
このスペースを膝窩筋腱が横断して走行しており、膝窩筋は膝外側部で独自の滑走経路を持ちます。
そのため、LCLと外側半月板を「つなぐ橋渡し的存在」として、膝外側の安定と滑走性の両立を担っているのです。
腓骨の安定化と膝窩筋の役割
膝窩筋は、膝窩腓骨靭帯を介して腓骨頭を後方から支持しています。
この構造的特徴により、膝窩筋は「脛骨のみならず腓骨の後方安定化機構」としても重要です。
臨床では、近位脛腓関節不安定症(腓骨頭の可動性亢進)を伴う症例で、膝窩筋および膝窩腓骨靭帯の機能低下が認められることがあります。
この場合、膝窩筋の筋力回復と滑走改善を目的とした運動療法が不可欠です。
膝窩筋の機能解剖
膝窩筋の走行をベクトル的にみると、主に次の2つの作用を持ちます。
- 脛骨内旋作用(tibial internal rotation)
膝窩筋は膝屈曲初期に働き、下腿外旋方向への動きを制動します。
これにより、下腿外旋不安定症や「knee in toe out」姿勢における膝外側ストレスを防ぐ役割を果たします。 - 脛骨を大腿骨に押し付ける軸圧作用
膝窩筋は、脛骨を後方から大腿骨に押し付けるように作用し、**関節面の接触安定性(支点形成力)**を高めます。
これは、いわゆる「膝の動的支持力」として、荷重時の膝安定に貢献します。
臨床での評価と触診のポイント
膝窩筋は腓腹筋の深層にあるため、直接的な触診が難しい筋の一つです。
触診のコツは、膝関節を軽度屈曲させて腓腹筋の緊張を緩和させた肢位をとること。
その状態で、膝窩中央よりやや外側に深く圧を加えると、膝窩筋の収縮感を得やすくなります。
また、膝軽度屈曲位での内旋動作を行わせながら触れると、膝窩筋が明確に収縮するのを確認できます。
圧痛や硬結を認めた場合は、膝外旋過多・内反位姿勢・腓骨頭可動性の異常などを併せて評価すると良いでしょう。
臨床的意義:膝窩筋の過緊張と疼痛
膝窩筋の内旋制御作用が過剰に働くケースでは、下腿外旋方向への不安定性が強く、
- ランニング時の「knee-in toe-out」姿勢
- 膝外側痛や膝窩部痛
- 下腿外旋時のクリック感
といった症状を呈します。
このような症例では、膝窩筋の筋内圧が持続的に高く、安静時でも減圧しにくい場合があり、自発痛を伴うこともあります。
治療としては、腓骨頭モビライゼーションや軽度内旋運動による筋膜リリース・循環改善が有効です。
まとめ
膝窩筋は、膝外側後方に位置しながら、LCL・外側半月板・腓骨頭をつなぐ安定化の要として機能しています。
脛骨内旋と関節軸圧による支点形成作用を併せ持ち、膝関節の「静的+動的安定化」に深く関与します。
臨床では、膝外旋不安定症や膝窩部痛を評価する際、腓骨頭の動き・膝窩筋の緊張度・滑走性の3点を意識することが重要です。
膝窩筋を「膝を動かす筋」ではなく、「膝を支える筋」として捉える視点が、治療精度を高める鍵となります。