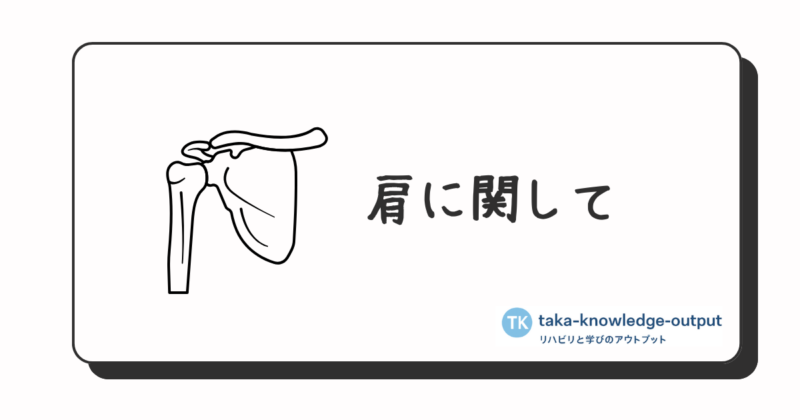リハビリがうまくいかない人の共通点|自己判断・依存・家族不在が回復を遅らせる理由

リハビリがうまくいかない人の共通点|自己判断・依存・家族不在が回復を遅らせる理由
前回の記事では、「リハビリがうまくいかない人」に共通する行動パターンの一つとして「自己判断による行動」を取り上げました。
今回はその続編として、わからないことを質問できない人・依存的な姿勢の人・家族の協力を得られない人という3つの側面から、臨床的に重要なポイントを掘り下げます。
「わからないことを聞けない」ことが大きな落とし穴に
患者が「自分の身体のことだから」と思い込み、細かいことを質問せずに自己判断してしまうケースは非常に多く見られます。
しかし、患者にとって「些細なこと」でも、療法士から見れば非常に重要な注意点であることが少なくありません。
たとえば、
- 「この角度までなら動かしていいと思った」
- 「装具は寝るときだけ外していいと思った」
- 「シャワーくらいなら問題ないと思った」
といった自己判断が、再損傷や癒着の原因になることがあります。
臨床家の立場からすると、これらの誤解を防ぐ最も効果的な方法は、「質問しやすい関係性」を作ることです。
「どんな小さなことでも聞いてくださいね」と伝えるだけで、患者の行動は変わります。
「質問=迷惑」ではなく「質問=安全な回復への一歩」と捉えてもらうように促しましょう。
家族の協力があるかどうかで回復スピードが変わる
もう一つ重要な要素が家族の同席とサポートです。
患者本人は自分の身体に対して過信や焦りを持ちやすく、「これくらいなら大丈夫」と思ってしまう傾向があります。
一方、家族は患者を心配する立場から、安全性を優先してブレーキ役になれる存在です。
そのため、
- 手術前後の医師説明に家族も同席してもらう
- リハビリの見学や生活指導を家族と一緒に受けてもらう
- 在宅での生活動作を家族が見守る体制をつくる
こうした取り組みは、安全で効果的なリハビリの継続につながります。
臨床家としては、リハビリ内容を本人だけでなく家族にも説明し、家庭でのサポート体制を整える意識が必要です。
「依存的な患者」は要注意——リハビリは“やってもらう”ものではない
リハビリがうまくいかない人のもう一つの特徴が、**「リハビリを受ける=療法士にやってもらうもの」**という受け身の姿勢です。
特に入院中は毎日リハビリを受けられる環境が整っているため、「先生にやってもらえばよくなる」と思いがちです。
しかし、外来通院になると週2〜3回が限界。
つまり、**1日のうちの23時間以上は「自分のリハビリの時間」**なのです。
理学療法の本質は、「脳が筋肉に命令を出し、自分の意志で身体を動かすこと」。
そのため、他人が動かすだけでは本当の意味での機能回復は得られません。
臨床家が担うのは、患者に「正しい動かし方を教えること」と「安全な範囲を確認すること」。
リハビリは**“教わって、自ら行うもの”**という意識を患者に育てる必要があります。
セルフリハビリを成功させる「宿題」の重要性
依存的な患者から主体的な患者へと変わるためには、**セルフリハビリ(自主トレーニング)**の導入が不可欠です。
多くの療法士は自宅での宿題を提示しますが、患者によっては「気が向いたらやる」程度になってしまうこともあります。
主体性の高い患者は、宿題の意味を理解しています。
「この運動を続けると関節が固まらない」「筋力が戻りやすくなる」など、目的を理解したうえで継続できるのです。
ただし、自主練習の強度・回数・頻度を誤ると、痛みの悪化や再損傷のリスクがあります。
そのため、宿題を出す際には必ず
- 正しいフォーム
- やり過ぎたときのサイン
- 次回来院までの目安
を明確に説明し、記録や動画などで確認できる形にするのがおすすめです。
まとめ:リハビリの成功は「質問・家族・主体性」の三本柱
リハビリがうまくいかない人の多くは、
- わからないことを質問できない
- 家族の協力が得られていない
- 自分でリハビリをやらない(依存的)
という共通点を持っています。
臨床家として重要なのは、患者を責めるのではなく、環境と理解の不足を補うこと。
質問しやすい関係を築き、家族を巻き込み、主体性を育てることで、リハビリの成果は確実に変わります。