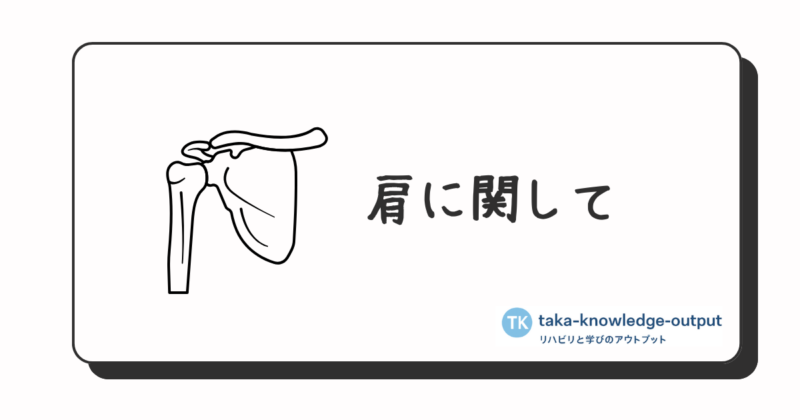「ゴールを徹底的に考え抜く」――リハビリの限界を突破する3ステップ

「ゴールを徹底的に考え抜く」――リハビリの限界を突破する3ステップ
手術も薬もリハビリも万能ではありません。どれだけ適切に介入しても、望んだレベルに届かないケースはあります。それでも私たちはそこで思考停止しないことが大切です。限界を感じた“その瞬間”こそ、ゴールを徹底的に考え抜くタイミングです。ゴールは結果を決める羅針盤であり、患者の行動と情動(やる気・希望)を同時に駆動させます。
ステップ1:ゴールを洗い出し、優先順位をつける
まず、患者が「回復したらやりたいこと」をとにかく書き出す。最初から立派な目標である必要はありません。日常動作から趣味、仕事、役割まで幅広く。
次に重要度×実現意欲で優先順位をつけます。ここで「実は今の状態でもできること」が見つかることが少なくありません。できていることに光を当てるだけで、患者の自己効力感は上がります。
ステップ2:「本当に諦めるべきか」を再検討する
限界に見える目標でも、手段の再設計で突破できる場合があります。
例:60代男性。腱板断裂手術後、ゴルフのバックスイングで痛みが残存。
動作分析で痛みが出る肩運動の局面を特定し、スイング軌道・体幹の使い方・グリップ・テイクバックの速度を調整。結果、疼痛なしで飛距離UPという新しいフォームに到達しました。
「目標を諦める」かどうかの前に、方法を変える余地がないかを徹底的に探ります(装具・代償動作・環境調整・頻度/強度の微調整など)。
ステップ3:まったく新しいゴールを再構築する
“過去に戻る”ことを目標にすると、達成困難なほど苦しくなります。そこで未来志向のゴールを設定します。ルールは2つ。
- できない理由は一旦すべて無視(資金・時間・人脈・年齢などの制限は脇に置く)
- 「上がる」ものを選ぶ(ワクワク・誇らしさ・使命感などポジティブ情動が上がるか)
先の男性は「プレー」に固執せず、「研究・指導」に喜びを見出して**“学び教えるゴルフ”**へとゴールを再設計。自らの経験を強みに変え、機能の限界をキャリアの可能性へ転換しました。
臨床家が伴走するための実践ポイント
- 言語化の支援:面談で「やりたいこと30個」を制限時間内で書き出し→上位5つを選ぶ。
- 試行の設計:痛みの出る局面を分解し、条件を一つずつ変える“ABテスト”で再挑戦。
- 情動の指標化:各ゴールに0–10で“上がる度”を採点し、数値が高い順に着手。
- チーム連携:医師・療法士・トレーナー・家族で「目標・役割・評価指標」を共有。
- 再評価の周期化:2〜4週ごとにゴールを再点検し、優先順位と手段をアップデート。
まとめ:ゴールは“結果”ではなく“エンジン”
限界を感じたとき、必要なのは努力の量ではなく目的の再設計です。
- 洗い出して順位づける
- 諦める前に方法を変える
- 未来志向で“上がる”新ゴールをつくる
この3ステップは、身体機能の回復だけでなく、患者の生き方の回復を後押しします。
「あなたのゴールは何ですか?」――その問いを、今、もう一度。