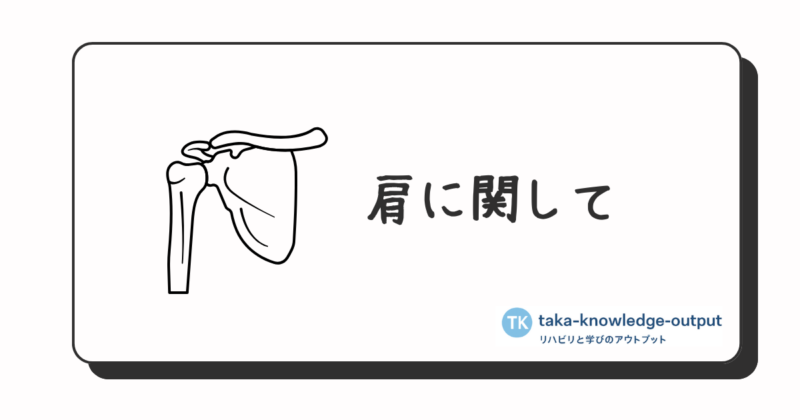神経障害性疼痛とは?画像所見と一致しない痛みをどう捉えるか

画像所見と痛みは一致しない
臨床において、画像所見と痛みの強さが一致しない ケースは少なくありません。
例えば、腱板断裂・膝関節症(OA)・脊椎症などでは、MRIやX線で構造的な異常が確認できても、それが必ずしも患者さんの訴える痛みの原因とは限らないことが多々あります。
そのため、整形外科領域では「本当に断裂部が痛みの原因か」を確認する目的で、局所麻酔薬を注入して疼痛の変化を観察する ことがあります。
- 局所麻酔を入れて痛みが軽減 → 損傷部が痛みの原因と判断
- 局所麻酔を入れても痛みが変わらない → 原因は他にあると判断
このようにして「画像に映る構造異常=痛みの原因」とは限らないことが明確になります。
画像で説明できない痛みの正体:神経障害性疼痛
画像で確認できる構造異常が痛みの原因でないと分かったとき、次に考えるべきは 神経障害性疼痛 です。
神経障害性疼痛とは、神経系の損傷または機能障害によって引き起こされる痛み のことです。
痛みの発生経路は「末梢神経 → 脊髄 → 脳」へと続きますが、その経路上のどこかで障害が起きても痛みは発生します。
つまり、構造的な異常がなくても、神経そのものに問題があれば痛みは生じる のです。
神経障害性疼痛の特徴
神経障害性疼痛には、侵害受容性疼痛とは異なる特徴的な症状があります。
- 灼熱感(焼けるような痛み)
- 鋭い痛み(ナイフで刺されるような感覚)
- しびれ感
- 電撃様の痛み(電気が走るような感覚)
- アロディニア(触れただけで痛みを感じる現象)
これらの症状は、筋骨格系の炎症や損傷に伴う典型的な痛みとは異なり、神経の異常を示唆する重要なサインとなります。
神経障害性疼痛は「特殊なケース」だけではない
神経障害性疼痛と聞くと、
- 外傷による神経損傷
- 糖尿病性神経障害
- 帯状疱疹後神経痛
など、特別な疾患や明確な損傷を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし実際には、日常的に遭遇する痛みの中にも神経障害性疼痛は存在する ことを認識しておくことが重要です。
例えば、長引く腰痛や肩の痛み、慢性的なしびれを伴う痛みなどは、画像所見だけでは説明できない場合が多く、神経障害性疼痛の可能性を考える必要があります。
臨床での評価の視点
理学療法士・作業療法士が臨床で神経障害性疼痛を評価する際には、以下の視点が有効です。
- 画像所見と症状の不一致を見逃さない
→ 構造異常だけで説明できない痛みは神経障害性を疑う。 - 特徴的な症状の有無を確認する
→ 灼熱感・電撃痛・アロディニアなどがないか詳細に問診する。 - 身体診察で神経経路を推定する
→ 感覚検査や誘発テストを行い、どの神経が関与しているかを推定する。 - 仮説を立てて介入し、反応を確認する
→ 末梢か中枢か、どのレベルでの障害かを明確にして治療戦略を組み立てる。
まとめ
- 画像所見と痛みは必ずしも一致しない
- 構造異常が痛みの原因でない場合、神経障害性疼痛を疑う
- 神経障害性疼痛は、灼熱感・電撃痛・しびれなど特徴的な症状を呈する
- 特別な疾患に限らず、日常的な慢性疼痛の中にも存在する
- 臨床では、画像だけでなく身体診察と問診による評価が不可欠
神経障害性疼痛を正しく捉えることは、痛みの原因を見誤らず、適切なリハビリテーションへとつなげるために非常に重要です。