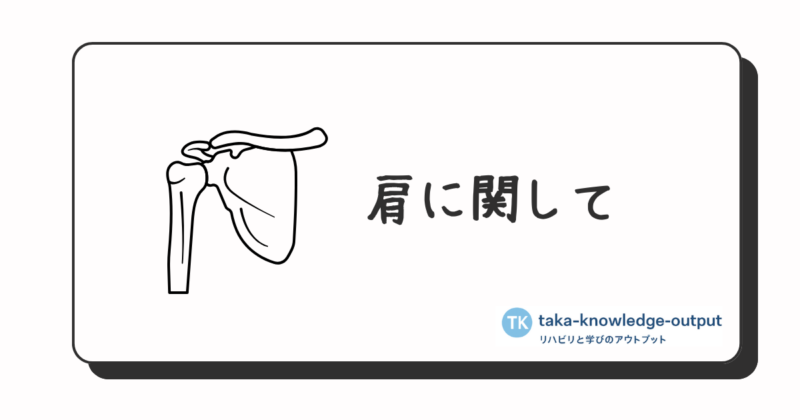筋攣縮と筋短縮の違いを理解する:理学療法士が押さえておきたい臨床的視点

筋攣縮と筋短縮 ― 臨床で混同されやすい二つの病態
理学療法の現場で「筋が硬い」「伸びにくい」といった症状に出会うことは多いですが、その背景にある病態は必ずしも同じではありません。
特に「筋攣縮(spasm)」と「筋短縮(contracture)」は、一見似たような臨床所見を示しますが、生理的機序や治療アプローチは大きく異なります。
本記事では、両者の違いを生理学的観点と臨床評価の2つの視点から整理します。
🔹 筋攣縮(spasm)とは
筋攣縮とは、筋が痙攣したように収縮した状態を指し、しばしば**血管のスパズム(連縮)**も伴います。
■ 生理的機序
関節周囲の組織が物理的・化学的刺激を受けると、侵害受容器が反応し、その信号は脊髄に入力されます。
この刺激は、
- 脳へ伝達される上行経路
- 脊髄反射を介して筋・血管へ伝わる下行経路
の2方向に分かれます。
このうち、筋攣縮に強く関係するのが脊髄反射です。
長期的に筋・血管の連縮が持続すると、局所の血流は停滞し、虚血による組織変性が起こります。
その結果、発痛物質が産生・感作され、疼痛や可動域制限を引き起こす悪循環(負のスパイラル)が形成されます。
この過程が進行すると、最終的に関節拘縮を助長することもあります。
🔹 筋短縮(contracture)とは
一方、筋短縮とは筋の伸長性が欠如した状態です。筋の「柔軟性」が低下し、構造的な制限が中心に存在します。
■ 生理的機序①:筋実質部の伸展性低下
筋繊維の基本単位である筋節(サルコメア)の数が減少することで、筋全体の伸展性が低下します。
通常、筋を伸ばすと細いフィラメントが太いフィラメントから引き離され、筋節間距離が延長します。
しかし筋節数が少なくなると、伸展に対する抵抗が増し、結果的に筋の硬さとして臨床上現れます。
■ 生理的機序②:筋膜・筋内膜の繊維化
関節の不動や運動不足により、筋膜や筋内膜のコラーゲン分子間に架橋結合が形成されます。
これによりコラーゲン量が増加し、組織の硬度が上昇。
つまり、筋膜の繊維化=伸展抵抗が増す状態と言えます。
🧩 筋攣縮と筋短縮の臨床的な見分け方
① 圧痛の有無
- 筋攣縮:圧痛を認めやすい(痛みを伴う過緊張)
- 筋短縮:圧痛は少ない(構造的硬さ)
② 伸張位と弛緩位での緊張変化
- 筋攣縮:
- 伸張位で緊張がさらに増強し、疼痛が出現しやすい
- 短縮位でも触診上の緊張が高い
- 筋短縮:
- 伸張位では緊張が高くなるが、短縮位では緊張が低下
③ 筋力低下と等尺性収縮時痛の有無
- 筋攣縮:
- 筋力低下を認める
- 強い等尺性収縮で疼痛が出現しやすい
- 筋短縮:
- 明らかな筋力低下は少ない
- 等尺性収縮で疼痛は出現しにくい
🧠 理学療法士が意識すべき臨床応用
筋攣縮は神経反射を介した動的な過緊張であるため、リラクゼーションや軽度の持続伸張、温熱療法などで改善が期待できます。
一方、筋短縮は組織構造の変化が関与するため、長期的なストレッチングや運動療法、姿勢修正などのアプローチが重要です。
また、評価時には「触診」「筋長テスト」「収縮時痛」「圧痛部位」などを総合的に捉え、病態の本質を見極めることが必要です。
🩰 まとめ
| 項目 | 筋攣縮 | 筋短縮 |
|---|---|---|
| 原因 | 反射性収縮(神経性) | 構造的短縮(筋・筋膜) |
| 圧痛 | あり | 少ない |
| 筋力低下 | あり | 目立たない |
| 伸張位での緊張 | 増強 | 増強(ただし短縮位で低下) |
| 代表的治療 | リラクゼーション、温熱 | ストレッチ、運動療法 |
筋の「硬さ」は単一の原因ではありません。
筋攣縮か筋短縮かを見極めることが、適切な理学療法アプローチにつながります。