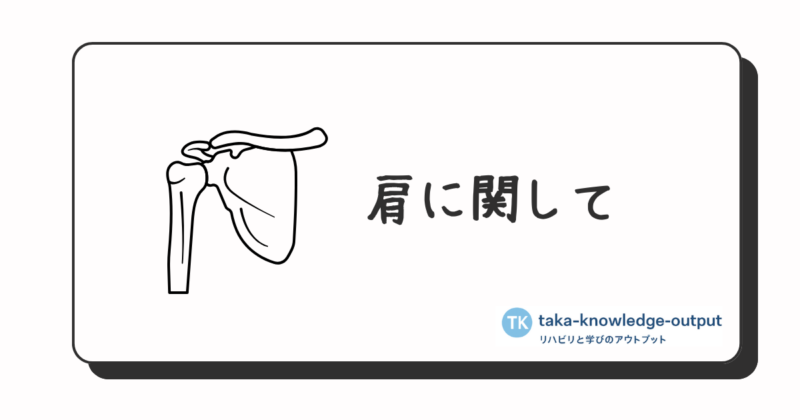顔面のSMAS(表在性筋膜系)とは?構造・機能・臨床での重要性をわかりやすく解説

顔の構造を支える「SMAS」とは?
SMAS(Superficial Musculoaponeurotic System:表在性筋膜系)は、顔面の皮膚と深部構造の間に存在する線維性ネットワークです。
この層は主に広頚筋(platysma)、耳下腺筋膜、そして頬部を覆う線維筋層から構成され、皮下脂肪と深部脂肪を隔てています。位置的には、頬骨弓(zygomatic arch)より下方、広頚筋の上方に存在します。
SMASは、顔の動きや表情を皮膚に伝達する“中間層”としての役割を果たし、顔のたるみや加齢変化にも深く関わります。1976年にMitzとPeyronieによって初めて詳細に記述されて以来、その定義や構造は長年議論されてきました。
構造と機能:5層構造の中の第3層
顔面は主に次の5層で構成されます:
- 皮膚(表皮と真皮)
- 皮下脂肪層
- 筋膜層(SMASを含む)
- 疎性結合組織または深部脂肪層
- 骨膜・深筋膜
SMASはこのうち第3層にあたり、表情筋の動きを皮膚に伝える“アポニューロティックマスク”として機能します。つまり、SMASがあることで、私たちは滑らかに笑ったり、怒ったり、驚いたりといった表情を作ることができます。
また、SMASは顔面の各部位で構造が異なり、鼻唇溝(nasolabial fold)より外側の領域では脂肪が多く柔軟で、内側では脂肪が少なく密な構造を持ちます。この違いが、顔の可動性や表情の豊かさに影響しています。
血管・神経支配
SMASは主に**顔面神経(第Ⅶ脳神経)**によって支配されています。
顔面神経は耳の下から出て、側頭枝・頬骨枝・下顎縁枝などの枝を形成し、SMASの深層を走行します。特に手術や注入療法(ボトックスなど)を行う際には、これらの神経損傷を避けるための解剖理解が不可欠です。
血流は**顔横動脈(transverse facial artery)**などが供給し、リンパは耳前・顎下リンパ節を経て頸部リンパ系へと流れます。
表情筋との関係
SMASは、以下の表情筋と密接に連結しています:
- 眼輪筋(orbicularis oculi)
- 口輪筋(orbicularis oris)
- 前頭筋(frontalis)
- 上唇挙筋(levator labii superioris)
これらの筋の収縮がSMASを介して皮膚に伝わることで、表情が生まれます。特に口輪筋や眼輪筋は、SMASの構造変化によりしわやたるみが目立ちやすくなるため、美容領域では重要なターゲットとなります。
臨床での意義:老化・手術・リハビリ
加齢による皮膚や脂肪の下垂は、SMASの弛緩と関係しています。美容外科で行われる**フェイスリフト(rhytidectomy)**では、SMASを引き上げることで顔全体の若返り効果を得ます。実際、約半数以上のフェイスリフト術において、SMASの操作が行われていると報告されています。
理学療法や顔面神経麻痺のリハビリにおいても、SMASの理解は欠かせません。例えば、ベル麻痺や重症筋無力症などではSMASの萎縮や線維化が生じ、表情の左右差や筋収縮の伝達異常を引き起こします。
また、慢性的な表情筋緊張やストレスによる顔面硬直も、SMASの過緊張や柔軟性低下が関係していると考えられます。理学療法士が表情筋リリースや顔面マッサージを行う際、この層を意識した介入はより効果的です。
まとめ
SMASは、単なる「顔の筋膜」ではなく、表情・加齢・美容・リハビリすべてに関わる重要な層です。
顔面の動きやたるみを理解する上で、この層をどれだけ正確に把握できるかが、臨床の質を左右します。
美容医療やフェイシャルリハビリに携わる専門職にとって、SMASの解剖学的知識は必須の教養といえるでしょう。