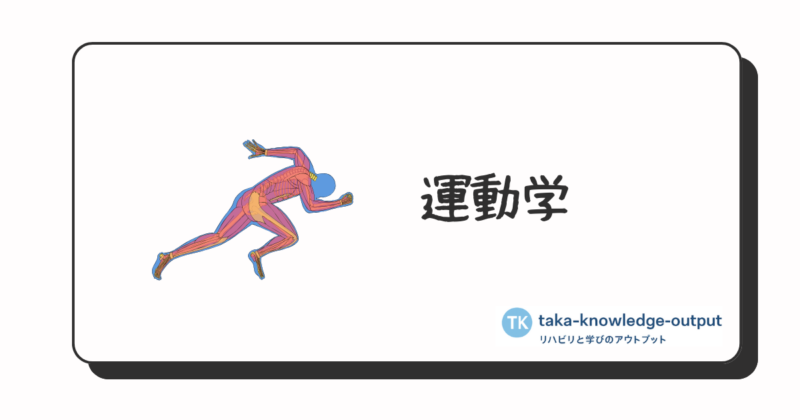側頭頭頂筋膜(Temporoparietal Fascia)とは?構造・機能・臨床的意義を専門的に解説

側頭頭頂筋膜(TPF)とは?
**側頭頭頂筋膜(Temporoparietal Fascia, TPF)**は、側頭部皮下に存在する薄い筋膜層で、別名「浅側頭筋膜(superficial temporal fascia)」とも呼ばれます。厚さは約2〜3mmで、頭皮から鎖骨まで連続する筋膜ネットワークの一部です。
この筋膜は、**頬部の表在性筋膜系(SMAS)と連続しており、さらに頸部の広頚筋(platysma)へとつながります。これにより、顔から首へと一体化した筋膜構造が形成されています。前方では眼輪筋(orbicularis oculi)および前頭筋(frontalis)と、後方では後頭筋(occipitalis)**と連続し、顔面表情筋の動きや皮膚張力の伝達に関与します。
層構造と位置関係
TPFは、皮膚から頭蓋骨に至る層構造の中で、上から3番目に位置します。
- 皮膚
- 皮下組織
- 側頭頭頂筋膜(TPF)
- 無名筋膜(innominate fascia)
- 深側頭筋膜(deep temporal fascia)
- 側頭筋(temporalis muscle)
- 骨膜(pericranium)
- 頭蓋骨(cranium)
TPFの下層にある「無名筋膜」は疎性結合組織で、TPFと深側頭筋膜を隔てる可動性の高い層です。この構造により、頭皮全体が滑らかに動くことが可能になります。
構造と機能
側頭頭頂筋膜は、顔面や頭皮の皮下構造を包み込み、血管・神経・筋肉を保護・整理する役割を担っています。
また、TPFがSMASや広頚筋と連続していることにより、顔面表情や咀嚼、頸部運動時に張力伝達の連動性が保たれています。
さらに、浅層の可動性と深層の安定性を兼ね備えることで、頭皮全体の「動き」と「安定性」を両立しています。これは、表情変化や咬筋の動きにも影響し、フェイシャルバランスの維持に欠かせません。
血管と神経支配
TPFは、**外頸動脈の終枝である浅側頭動脈(superficial temporal artery)**によって豊富に栄養されています。この動脈は耳前部の耳下腺を貫通して走行し、頭皮や筋膜への血流を供給します。
静脈は同名の浅側頭静脈が還流を担い、リンパは耳前・後耳介・後頭リンパ節へと流れます。頭皮にはリンパ節が存在しないため、感染や浮腫が広がりやすい特徴があります。
神経支配では、顔面神経(第Ⅶ脳神経)の側頭枝がTPF内を走行します。特に手術時にはこの神経の走行に注意が必要です。神経は耳下腺を出たのち、頬骨弓の上約1.5〜3cm、外眼角の後方0.9〜1.4cm付近でTPFの下面に移動するため、この領域は「筋膜移行帯(fascial transition zone)」として重要視されます。
感覚神経は、三叉神経の枝(前頭・頬骨・耳介・後頭神経など)が支配しています。
臨床的意義と手術応用
■ 再建外科での活用
側頭頭頂筋膜は、血流が豊富で柔軟性が高いため、再建外科領域で広く利用されています。
1898年には、耳介損傷(馬咬傷後)や下眼瞼の再建に初めて用いられました。現在では以下の用途が知られています。
- 額・眉・耳・唇の再建
- フェイスリフト(側頭部挙上)時の補強
- 瘢痕や脱毛防止のための筋膜縫縮(plication)
最大約14cmのTPFフラップが安全に採取可能で、筋膜・皮弁・骨膜付き皮弁として利用できます。
■ 耳科手術での利用
耳小骨手術(鼓膜形成術:tympanoplasty)では、**側頭筋膜(temporalis fascia)**が自家移植材料として頻用されます。採取が容易で、鼓膜の部分的・全体的欠損修復の両方に適しています。
理学療法との関連
側頭頭頂筋膜は、表情筋や咀嚼筋群の張力伝達経路として機能し、咬筋・側頭筋・広頚筋などとの連動が強い構造です。
そのため、顎関節障害(TMD)や顔面痛、頭痛の治療においても、TPFの滑走性や緊張バランスを評価することは有用です。
また、筋膜連鎖の観点から、頭頸部の筋膜緊張は肩・胸郭・姿勢制御にも影響を与えるため、全身的アプローチの一環としてTPFを意識した手技介入が有効です。
注意点と合併症
TPFは血流が良好で信頼性の高いフラップですが、血管損傷による壊死リスクがあります。
特に、熱傷・外傷・過去の頭部手術歴のある患者では血行が損なわれている可能性があるため、採取や操作は慎重に行う必要があります。術前にはドップラー検査による血流確認が推奨されます。
まとめ
側頭頭頂筋膜は、顔面の構造的安定性・表情・再建外科など多方面で重要な役割を果たす結合組織です。
その位置関係や神経走行を正確に理解することは、美容外科・耳鼻咽喉科・理学療法いずれの分野においても不可欠です。
解剖学的知識をもとに、頭頸部の動態や筋膜連鎖を理解することで、より安全で効果的な臨床介入が可能になるでしょう。