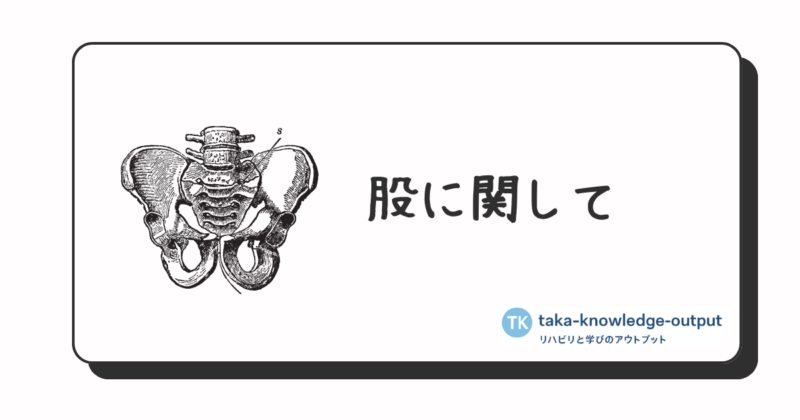膝蓋下脂肪体は残すべきか?―人工膝関節置換術後の前膝部痛を減らすRCTの示唆

膝蓋下脂肪体は残すべきか?―人工膝関節置換術後の前膝部痛を減らすRCTの示唆
人工膝関節置換術(TKA)後の満足度を左右する要因の一つが前膝部痛(AKP)です。術式やインプラント設計の進歩にもかかわらず、AKPは依然として無視できません。近年注目される組織が膝蓋下脂肪体(infrapatellar fat pad:IPFP)。視野確保のため切除されることもありますが、温存か部分切除かで疼痛に差が出るのか――この問いに正面から取り組んだ**無作為化比較試験(RCT)**が報告されました。
研究デザインの要点
対象は一次性内反変形(20°未満)のTKA患者。コンピュータ支援手術を用い、術中プロトコルと術後リハは両群で統一。ランダム化でIPFP部分切除群(主に膝蓋腱内側部)と温存群に割り付け、**AKPの発生率と痛みの強さ(VAS)を主要評価項目として、1・3・6・12か月で追跡。補助評価としてROM、修正WOMAC、機械的アライメント、Insall–Salvati比(ISR)を測定しました。解析対象は57例(切除27・温存30)**です。
結果:早期(1か月)に明確な差
1か月時点でAKPは切除群77.8%、温存群33.3%と温存が有意に良好。VASも温存群で低値でした。一方で3・6・12か月では群間差は消失。ROM、MA、ISRにも一貫した差はなく、パテラ短縮(ISR低下)は認められません。修正WOMACは6か月で統計学的差が出たものの、最小臨床重要差(MCID)未満で臨床的意義は限定的と解釈されました。
臨床的インプリケーション(理学療法士向け)
- 早期疼痛コントロール:IPFP温存は術後1か月のAKP軽減に寄与。早期離床・自主訓練の受容性を高め、可動域や歩行練習の立ち上がりを後押しします。
- 痛みの見通し提示:部分切除が行われたケースでは1〜3か月のサブアキュート期に疼痛が強い可能性を説明し、活動量と鎮痛の計画を個別化。
- 運動療法の組み立て:温存・切除いずれでもROM回復・大腿四頭筋機能再建を柱に。膝蓋腱周囲の機械刺激を抑えつつ、段階的荷重・屈伸角の進行を管理。疼痛が強い症例ではペーシング、座位でのCKC軽荷重練習、電気刺激の補助などで閾値を下げる。
- 組織保護の視点:本試験ではパテラ腱短縮は示されませんでしたが、前膝部の摩擦増大や局所炎症を念頭に、**腫脹管理(RICEの適応的運用、圧迫・挙上の時間配分)と瘢痕癒着予防(ソフトタッチの徒手・滑走誘導)**を併用。
- アウトカム共有:長期(12か月)では群間差が乏しいため、短期の痛み軽減=長期機能の保証ではないと患者と共有し、WOMACや患者立脚型指標で経過を見える化。
なぜ温存で痛みが減るのか(考えうる機序)
本研究は機序解明を目的としていませんが、IPFPは血行供給や機械的緩衝・滑走に関与します。部分切除は早期の局所炎症・疼痛感受性を高めうる一方、温存は術創周囲の生体学的ホメオスタシスを保ちやすい――この差が1か月時点のAKPに反映された可能性があります。
限界と今後
単施設・サンプルサイズが限られ、AKPは主観評価である点、画像・バイオマーカーがない点、追跡1年で長期影響は不明です。とはいえ、術式・リハの標準化、評価者盲検化など内部妥当性は高く、「早期疼痛に関してはIPFP温存が有利」という臨床判断に現実的な根拠を与えます。今後は長期追跡と炎症マーカー/動的PF関節評価の併用が望まれます。
まとめ(実装ポイント)
- TKA後1か月のAKP低減にはIPFP温存が有効。
- 中期以降の痛み・機能差は限定的で、長期成績の鍵は包括的リハ戦略。
- 術式情報(温存/切除)を把握し、サブアキュート期の疼痛予測と運動処方を調整。
- 腫脹・滑走・負荷管理を細やかに行い、**早期の「動ける実感」**を引き出す。
早期の一歩を軽くすることが、その後の歩行自立や満足度に波及します。IPFPの扱いを理解し、術式に合った疼痛戦略で患者の回復を後押ししていきましょう。