大腿二頭筋断裂の病態と臨床的対応:膝OAにおける外側支持機構の脆弱化をどう見るか
taka
Taka Knowledge Output
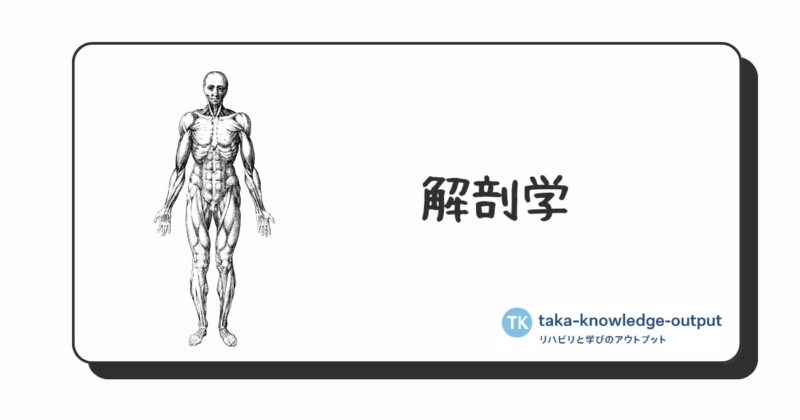
近年「筋膜リリース」などで注目される筋膜(fascia)。一見すると単純な膜組織に思えますが、国際的な学術団体はその定義をめぐって議論を重ねてきました。筋膜は単に筋肉を包む膜ではなく、全身を貫く結合組織のネットワークとして理解されつつあります。
国際解剖学連合(IFAA)のもとで活動する委員会は、筋膜を
筋膜研究学会から派生した委員会は、さらに広義の概念を提示しました。筋膜を「全身に連続するコラーゲンを含む結合組織の三次元ネットワーク」と捉え、腱・靭帯・関節包・髄膜・脂肪組織・骨膜・筋膜内の細胞外基質まで含めています。ここでは「連続性」と「多様な組織の統合性」が強調されています。
オステオパシー研究団体FORCEは、筋膜を「機械的刺激に反応する能力を持つ組織」と定義。皮膚・血液・リンパ・筋肉・神経周囲組織・臓器など、体内の多様な要素を含めて「力学的・代謝的な情報を伝達する連続体」としています。
複数の定義を整理すると、筋膜には以下のような役割があることがわかります。
このように筋膜は単なる膜ではなく、全身の統合的な健康に直結するシステムとして理解されています。
理学療法や作業療法の現場で「筋膜」を理解することは、以下の点で重要です。
筋膜は「筋肉を覆う膜」にとどまらず、全身を結びつけ、支え、情報を伝えるネットワークです。
学術的定義は多様ですが、共通しているのは「身体全体を一つに統合する重要なシステム」であるという点です。
健康を考える上で、筋膜を無視することはできません。