腋窩神経絞扼症候群(Quadrilateral Space Syndrome)とは?原因・症状・診断・治療を解説
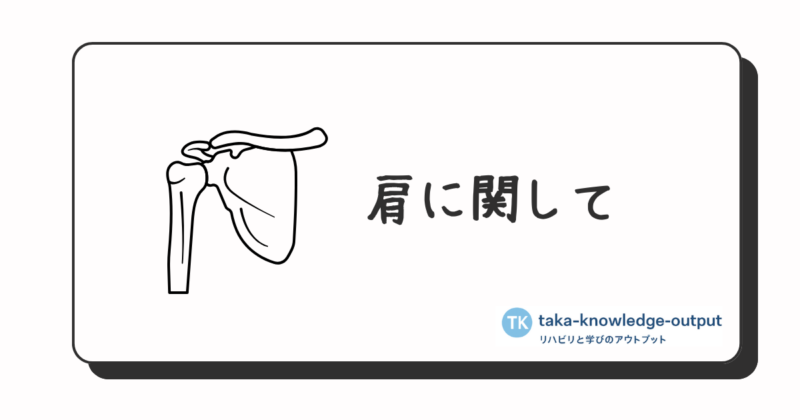
腋窩神経絞扼とは?
腋窩神経は肩の動きと感覚を担う重要な神経で、特に三角筋・小円筋を支配しています。外傷や肩関節脱臼、手術後合併症などで損傷されやすく、成人の肩周囲で最も多い単独の末梢神経障害とされています。その代表的な病態が 腋窩神経絞扼症候群(Quadrilateral Space Syndrome: QSS) です。
QSSは特に20〜40歳の男性オーバーヘッドアスリート(バレーボール・テニス・投球競技など)に多く見られ、発症機序としては 繰り返される外転・外旋動作 による慢性的なストレスが挙げられます。
解剖学的背景
腋窩神経は腕神経叢後索から分岐し、C5–C6を主根とし(時にC4由来もあり)、肩甲下筋の下縁を通って 四辺形間隙(quadrilateral space) を走行します。
四辺形間隙の境界は以下の通りです:
- 上:小円筋
- 下:大円筋・広背筋
- 内側:上腕三頭筋長頭
- 外側:上腕骨外科頸
このスペースを通過した腋窩神経は前枝(前部三角筋を支配)と後枝(後部三角筋・小円筋・外側上腕皮神経枝)に分かれます。同伴する血管は 後上腕回旋動脈 です。
この狭い空間で神経・血管が圧迫されるのがQSSの本態です。
発症メカニズムと原因
QSSの原因は 静的因子 と 動的因子 に分けられます。
- 静的因子
- 線維性バンド(小円筋と上腕三頭筋長頭の間に形成されやすい)
- 腫瘍・嚢胞・血腫などの占拠性病変
- 筋肥大による空間狭小化
- 骨折後変形や骨棘
- 動的因子
- 外転・外旋位での神経・血管圧迫
- 投球動作やスパイク動作に伴う反復性マイクロトラウマ
特にスポーツ選手では 筋肥大や線維性バンド が主要因とされ、解剖学的スペースの減少により症状が出現します。
症状
腋窩神経絞扼の主な症状は以下の通りです:
- 鈍い肩後方〜外側の痛み(夜間痛あり)
- 上腕への放散痛やしびれ感(非皮節性)
- 三角筋・小円筋の萎縮(慢性例)
- 外転・外旋での疼痛増悪
- 疲労感や肩のだるさ
血管も同時に圧迫される場合(血管型QSS)には、手指の冷感・蒼白・脈拍減弱など虚血症状を伴うことがあります。
診断
診断は難しく、臨床家の「疑い」が重要です。
- 身体所見
- 四辺形間隙の圧痛
- 外転・外旋位での症状誘発
- 三角筋・小円筋の萎縮や筋力低下
- 画像・検査
- MRI・CT:筋萎縮や占拠性病変の評価、線維性バンドの描出
- EMG/NCV:神経伝導異常の確認(偽陰性あり)
- 超音波:嚢胞・腫瘍などの描出、ダイナミック評価
- 血管造影:血管型QSSの評価(ただし偽陽性が多い)
- リドカインブロックテスト:四辺形間隙への局麻注射で疼痛が軽快すれば陽性
治療
保存療法
まずは非観血的治療が推奨されます(6か月間が目安)。
- 活動制限・競技動作の修正
- 鎮痛薬・物理療法
- リハビリ(肩甲骨安定化、後方ローテーターカフ強化、ストレッチ)
多くの症例は保存療法で改善します。
手術療法
適応となるのは:
- 占拠性病変が原因の場合
- 保存療法に6か月以上反応しない場合
- 陽性のリドカインブロックテストがある場合
手術法にはオープン減圧術(線維性バンド切除、腫瘍摘出など)と関節鏡下手術があります。近年は関節鏡下アプローチが増えており、関節内病変への同時対応も可能です。
術後は可動域訓練から開始し、競技復帰は6週以降を目安とします。
まとめ
腋窩神経絞扼症候群は稀ながら、肩痛やパフォーマンス低下を引き起こす疾患です。オーバーヘッドアスリートや術後例では特に注意が必要です。
臨床家としては、
- 四辺形間隙の圧痛や三角筋・小円筋の萎縮に注目すること
- 他疾患(腱板損傷・頸椎病変など)との鑑別を徹底すること
- 保存療法と外科的治療の適応を整理し、医師と連携すること
がポイントになります。




