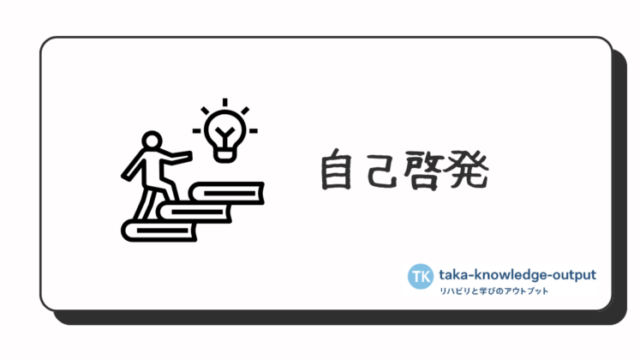『デフレの正体と統計の罠:需要不足が招く停滞』

デフレの真因は「総需要の不足」にある
日本経済を長きにわたり蝕んでいる「デフレ」。その原因について、まことしやかに語られる言説がある。「少子高齢化が原因だ」「人口減少のせいだ」、あるいは「若者の欲望が減退したからだ」といった精神論である。しかし、経済学的な視点に立てば、それらは本質的な原因ではないと断言できる。デフレの正体、それは単純にして深刻な「総需要の不足」である。
換言すれば、非合理的なまでに支出を恐れる政府が、財政赤字の拡大を忌避するあまり、消費や投資という需要を十分に創出できていないことが根本原因といえる。デフレ下の国において、モノやサービスを作る能力、すなわち「供給能力」が欠如しているわけではない。工場はあり、人は働き、サービスを提供する準備は整っている。しかし、それを買い取る「お客さん」が存在しない。これがデフレの冷徹な現実である。
供給能力と実需の乖離:デフレギャップの構造
この状況を企業の現場に置き換えて考えてみよう。ある工場に、1日に100個の製品を生産する能力があると仮定する。設備も整い、従業員も十分にいる。しかし、市場からの注文は90個しかない。この場合、供給能力である100から、実際の需要である90を差し引いた「10」が余剰となる。この需要の不足分こそが「デフレギャップ」と呼ばれるものである。
現在、日本には約30兆円規模のデフレギャップが存在すると言われている。これは、本来であれば生産され、誰かの所得になるはずだった30兆円分の富が、単に買い手がいないという理由だけで無に帰していることを意味する。さらに問題なのは、この数字自体が、実態よりもかなり過小評価されている可能性が高いという事実である。
統計に隠された「過小評価」のからくり
なぜ、デフレギャップは実態よりも小さく計算されてしまうのか。その原因は、内閣府や日本銀行が採用している「潜在GDP(供給能力)」の定義にある。本来、国民経済における供給能力とは、国内のすべての工場、機械、そして労働力がフル稼働した際に達成できる生産量、すなわち「最大概念の潜在GDP」であるべきだ。物理的に生産可能な最大値を基準にしてこそ、現在の稼働率の低さが浮き彫りになるからである。
ところが、現在の日本の統計では、過去の平均的な生産実績をもとに算出した「平均概念の潜在GDP」を基準としている。たとえば、本来200個作れる能力がある工場でも、不況で過去の平均生産量が95個だった場合、その「95個」を供給能力とみなしてしまうのだ。その結果、実際の需要が90個であれば、ギャップは本来の「110」ではなく、わずか「5」に縮小して計算される。つまり、不況が長引けば長引くほど「平均」が下がり、統計上の供給能力も低下するため、見かけ上のデフレギャップが消えてしまうというパラドックスが生じている。これでは、正しい経済対策など打てるはずがない。
経済再生への唯一の処方箋
誤った指標により「需要不足は大したことはない」と判断されれば、必要な財政出動が見送られ、デフレはさらに長期化する。この悪循環を断ち切るには、正しい現状認識を持つことが不可欠である。デフレの正体はデフレギャップ、つまり需要不足である。そして需要とは、消費と投資の合計に他ならない。
具体的には、私たちが日々行う「民間最終消費支出」、政府が行う「政府最終消費支出」、住宅や工場への投資である「民間住宅」「民間企業設備」、そしてインフラ整備などの「公的固定資本形成」。これに輸出から輸入を引いた「純輸出」を加えたものが総需要である。このうち、海外の景気に左右される輸出を日本がコントロールすることは難しい。だからこそ、国内で完結できる対策が必要となる。民間が弱っている今、政府が率先して消費と投資を増やし、需要の穴を埋めること。あるいは、消費税減税によって民間の購買意欲を喚起すること。そのためには、政府が一時的な財政赤字の拡大を恐れず、大胆な財政出動を行うことが、日本経済を再生させるための論理的かつ唯一の道筋であるといえる。