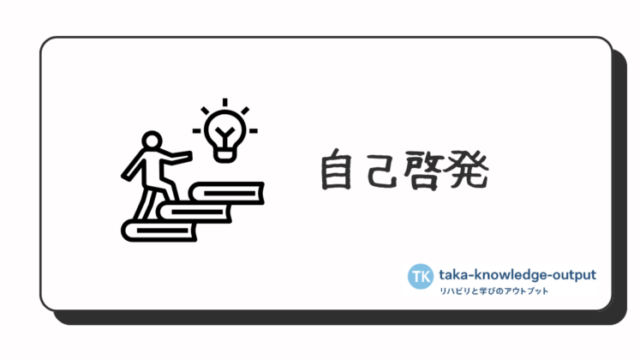『文明は森を食い尽くして滅ぶ。自給率12%の日本に迫る危機』

文明を支える「火」の代償
「エネルギー自給率」という言葉から、あなたは何を想像するだろうか。これは、我々の生産活動や日々の暮らしに必要な一次エネルギーのうち、どれだけを自国の資源で賄えるかを示す、国家の生命線ともいえる指標である。一次エネルギーとは、加工される前の自然の力を指す。石油、石炭、天然ガス、そして原子力や水力、太陽熱などがこれにあたる。
人類史を俯瞰してみれば、我々が最も長く依存し、そして消費してきたエネルギー資源は「木材」であった。煮炊きをし、暖を取る。火を使わなければ人間は生きていけない。石炭が産業の主役となる遥か以前、文明は森の木々を燃やすことで維持されていたのである。 しかし、木材という資源は、苗木から利用可能な大きさに育つまで何十年もの歳月を要する。消費のスピードが再生のスピードを上回ったとき、文明は衰退の道を辿る。古代メソポタミア文明が栄えたチグリス・ユーフラテス川流域は、かつて豊かな森林に覆われていたという。最古の文学『ギルガメッシュ叙事詩』がレバノン杉の森を舞台にしていることからも、その豊かさが窺える。だが、現在その地はイラクやシリアの乾燥した大地となり、かつての面影はない。人類の初期文明の多くは、森を食い尽くし、大地を砂漠へと変えることで終焉を迎えてきた歴史がある。
日本の山々が禿山だった時代
この列島においても、事情は同じである。日本の文明もまた、森林という一次資源に深く依存して発展してきた。かつて日本の中心地であった奈良盆地。ここに数百年もの間都が置かれ、数十万人が暮らしていれば、周辺の森林資源が枯渇するのは必然であったろう。 西暦七九四年、桓武天皇が長岡京を経て平安京へと遷都を行った背景には、奈良盆地周辺の木材を取り尽くし、建設や燃料のための資源が枯渇したという事情があったとする説も有力である。 時代は下り、江戸時代。葛飾北斎が描いた『富嶽三十六景』を仔細に眺めてみてほしい。そこには、青々とした森ではなく、禿山に松がまばらに生えているだけの荒涼とした背景が描かれていることが多い。当時の日本は、すでに森林資源の限界に直面していたのである。もし、その後のペリー来航を機に石炭という新たなエネルギー源への転換がなされなかったならば、日本の近代化は資源不足により確実に停滞していただろう。
崩れたバランスと12%の衝撃
現代において、国を動かす血液ともいえる電力。その発電構成比率を「エネルギーミックス」と呼ぶ。 二〇一〇年度の日本を振り返ると、LNG(液化天然ガス)が二八パーセント、石炭が二七パーセント、原子力が二六パーセント、水力が七パーセントと、特定の電源に偏らない理想的なバランスを保っていた。エネルギー源の多様化こそが、安全保障の要だからである。 しかし、二〇一一年の東日本大震災と原発事故がすべてを変えた。原子力の停止、そして天候任せで不安定な再生可能エネルギーの急拡大。その歪みを埋め合わせるために頼ったのは、結局のところ火力発電であった。二〇二〇年度には、LNGと石炭だけで全体の七割を占めるに至り、極端な火力一本足打法となってしまったのである。
ここで直視すべき現実は、LNGも石油も石炭も、日本はそのほぼすべてを海外からの輸入に依存しているという点だ。その結果、日本のエネルギー自給率は、OECD加盟国の中で下から二番目となる一二パーセントにまで低迷している。 かつての文明が森を失って衰退したように、現代の我々もまた、海外からの供給が途絶えれば即座に機能不全に陥る脆さを抱えている。この状況を「問題だ」と感じないことこそが、日本にとって最大の問題といえるのではないだろうか。