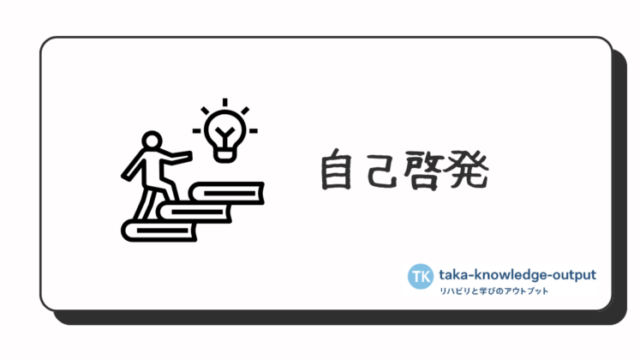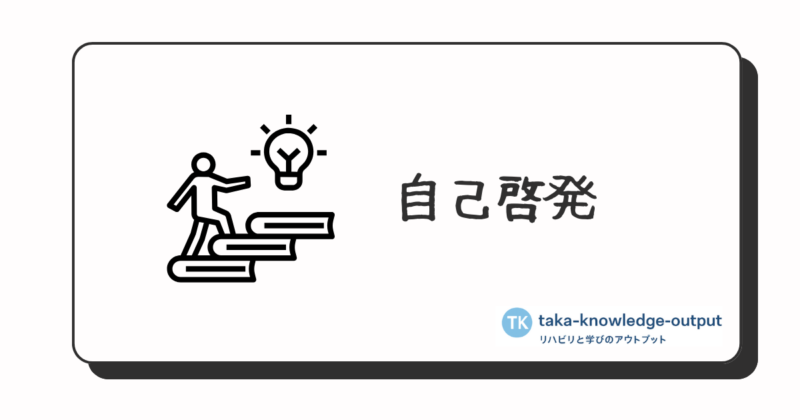『消費税は「預かり金」ではない?賃上げを阻む構造的欠陥』

「納税」とは「債務」の履行である
税金とは何か。多くの人は「国民の義務として払うもの」という感覚を持っているかもしれない。しかし、法的な定義において、その本質はよりドライで明確なものである。課税とは、国から一方的に設定される「債務」であり、納税者はその債務を履行する「債務者」に他ならない。一切のリターンが約束されないにもかかわらず、ある日突然、支払い義務という名の借金を背負わされるのが税の正体であるといえる。
ここで重要になるのが、言葉の定義である。「納税義務者」や「税金を負担する人」という曖昧な表現は、時に本質を覆い隠してしまう。重要なのは「誰がその租税債務を負っているか」という一点である。たとえば、入湯税を考えてみてほしい。この税の法的な債務者は入湯客である。しかし、実際に税務署へ納める手続きを行うのは温泉事業者だ。このように、債務者と納付者が異なる場合を「間接税」と呼ぶ。では、消費税はどうだろうか。消費税法において、納税義務を負う租税債務者は、消費者ではなく「事業者」と明記されている。つまり、事業者が債務を負い、事業者が納める。この定義に従えば、消費税は紛れもない「直接税」ということになる。
定義を歪める「転嫁」というレトリック
しかし、財務省の見解はこれとは異なる。彼らは「転嫁」、つまり税分を価格に上乗せできるかどうか、という基準を持ち出し、消費税を間接税であると説明する。だが、この論理には危うさがある。たとえば法人税が増税された際、企業が利益を確保するために商品価格を値上げしたとする。これも広い意味での「転嫁」だが、だからといって法人税を間接税とは呼ばないだろう。「価格に転嫁できるから間接税だ」という理屈は、本来明確であるはずの「誰が法的な支払い義務を負っているか」という事実を曖昧にし、議論を複雑化させている要因であるといえる。
賃上げを阻む「粗利税」の正体
直接税か間接税かという神学論争に決着がつかないのであれば、視点を変えて実態を見るべきである。消費税の計算式は、極めて単純化すれば「売上」から「仕入」を引いた残りに課税される仕組みだ。売上から仕入を引いたもの、それは企業会計でいう「粗利益(付加価値)」に他ならない。つまり、消費税の実態は、企業が生み出した付加価値そのものにペナルティを課す「粗利税」であると定義できる。
ここに見過ごせない問題がある。従業員の給与は、この粗利益の中から支払われる。粗利益そのものに課税されるということは、企業が人件費を上げようとすればするほど、あるいは利益を出そうとすればするほど、税負担が増える構造になっているのだ。消費税が「預かり金」ではなく、事業者が稼いだ粗利に対する課税である以上、それは構造的に賃上げを抑制する圧力として機能してしまう。経済成長と賃金上昇を目指す現代社会において、この税制が果たして最適解なのか。言葉の綾に惑わされず、その本質的な構造を見つめ直す必要がある。