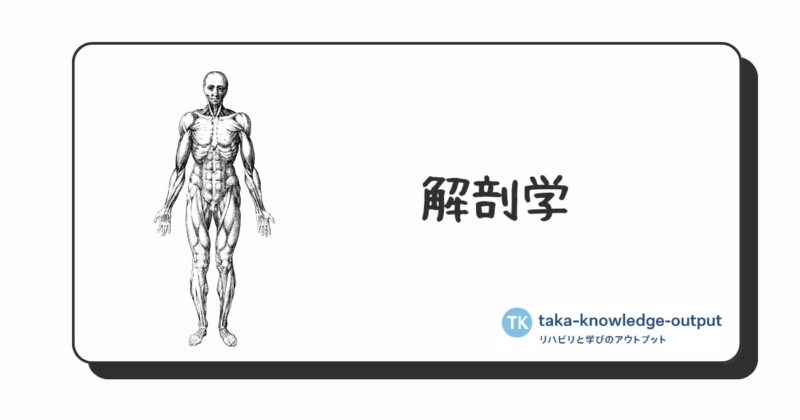Double Crush Syndromeとは?歴史・病態・臨床的意義を再学習する

ダブルクラッシュ症候群とは何か
**Double Crush Syndrome(ダブルクラッシュ症候群)**とは、近位の神経損傷が遠位の末梢神経を脆弱化させ、わずかな圧迫でも臨床症状を引き起こすとする仮説です。1973年にUptonとMcComasが Lancet 誌に発表したのが始まりです。
彼らは、手根管症候群のような末梢神経絞扼症候群を呈する患者の多くが、同時に頸部や肩、上腕に痛みを訴えることに着目しました。さらに、電気生理学的評価では70%の患者に頸神経根病変が認められたことから、「一つの神経が複数部位で障害を受けることで症状が顕在化する」というモデルを提唱しました。
UptonとMcComasによる病態モデル
彼らは脱神経の原因を以下のように整理しました:
- 圧迫がない場合 → 脱神経は起こらない
- 軽度の圧迫が単独で存在 → 症状は出現しない
- 近位+遠位での軽度圧迫が重複 → 軸索流が低下し臨床症状を惹起
- 遠位での強い圧迫 → 単独で症状を引き起こす
- 基礎疾患による脆弱性(例:糖尿病) → 軽度の圧迫でも症状が出やすい
特に③の「二重の圧迫によって症状が現れる」という部分が、ダブルクラッシュの核心です。
手根管症候群との関連
手根管症候群はダブルクラッシュ症候群の代表例としてよく取り上げられます。
- Crymble (1968) の報告では、手根管症候群患者の多くが手首だけでなく前腕・肘・肩・胸部に痛みを訴えていました。
- 一方で、局所的な神経損傷(切創など) では、そのような関連痛はほとんど見られません。
この差は「頸椎レベルの病変があることで、遠位の手根管圧迫が症状を顕在化させているのではないか」と考えられました。
さらに、Phalenの研究(1966)では、手根管を手術で展開した212例中61例で圧迫の明らかな所見が認められなかったことが報告されています。この点も「単なる局所因子だけでは説明できない」ことを示唆しています。
1980年代以降の知見
Hurstら(1985)は1,000例の手根管症候群を分析し、以下の病態モデルを提示しました:
- a 正常
- b 手根管で軽度圧迫(症状なし)
- c 頸椎障害+軽度圧迫(症状出現)
- d 手根管で強い圧迫(症状出現)
- e 軸索流の障害(糖尿病など)+圧迫(症状出現)
このように、近位・遠位の神経負荷、さらに全身的な要因が複雑に絡み合って症状が形成されることが整理されました。
臨床における意義
ダブルクラッシュ症候群は、以下の臨床場面で重要な視点を与えます:
- 手根管症候群手術後の改善不良
→ 局所の除圧だけでは不十分な場合、近位病変を見逃している可能性があります。 - 末梢神経障害に多部位の関連痛があるケース
→ 単なる局所因子だけでなく、頸部や肩の関与を考慮する必要があります。 - 基礎疾患を有する患者(糖尿病、甲状腺疾患など)
→ 神経栄養の低下が背景にあるため、圧迫の閾値が下がっている可能性があります。
まとめ
Double Crush Syndromeは「神経は一つの部位だけで障害されるのではなく、複数部位の小さな負荷が重なり合って症状を生じる」という視点を提供します。
画像診断が乏しかった時代の臨床家たちは、鋭い観察眼からこの仮説を導き出しました。現代の私たちは、エビデンスと臨床推論を組み合わせて、患者の複雑な症状を多角的に解釈する必要があります。
ダブルクラッシュ症候群を念頭に置くことで、
- 「局所だけをみて治療が進まないケース」
- 「原因不明の症状が長引くケース」
に新たな視点を加えることができるでしょう。