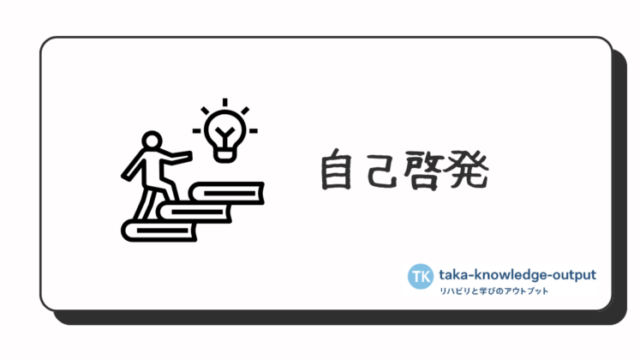「将来世代へのツケ」という最大の誤解

国の借金はツケではない
「国の借金は将来世代へのツケだ」──この言葉は長く日本社会に浸透してきた。
しかし、政府の債務は国民が背負う借金ではなく、返済の主体も国民ではない。
政府は自国通貨を発行でき、政府債務は増えていくのが現代の金融システムの基本構造である。
実際、政府債務を減らし続けている国など存在せず、どの国も必要な投資のために債務を積み上げている。
それこそが国家運営の当たり前の姿だといえる。
将来世代への投資こそが政府債務の役割
政府債務の増加は、未来の負担ではなく、むしろ未来への投資そのものだ。
教育、医療、社会インフラ、研究開発、防災──こうした分野への投資は将来世代を支える基盤となる。
政府が支出を抑えれば、これらの投資は削られ、未来の成長余地まで縮小してしまう。
つまり、国の借金が将来に負担を残すという発想自体が、現実とは逆の構造を作り出してきたといえる。
良心につけ込む「将来世代へのツケ」論
この言い回しが厄介なのは、国民の良心を利用して緊縮財政を正当化する点にある。
「子どもたちのために負担を減らさなければ」という正義感の強い人ほど、こうした主張に引き込まれてしまう。
だが、政府の債務を国民の借金として扱う前提自体が誤りであり、ミスリードそのものだといえる。
政府自身がその言葉を用い、メディアが繰り返してきたことで、誤解は社会の常識として固定化された。
緊縮財政が生んだ本当のツケ
本当の意味で将来世代にツケを残してきたのは、政府債務ではなく、緊縮財政である。
「国の借金が大変だ」という前提で予算が削られ、必要な投資が行われなかった。
その結果、経済は長く停滞し、平均賃金は下がり続け、かつて一億総中流と言われた社会は大きく崩れた。
成長が止まれば、所得は伸びず、国民生活は悪化する。
未来への投資を怠ったことで、まさに将来世代の豊かさが失われていったのである。
本当に残されたツケを見極める
改めて考えるべきなのは、将来に残すべきは負担ではなく基盤だという点である。
政府が適切に支出し、社会の成長力を高めることこそが、次の世代への責任を果たす道だといえる。
緊縮が続いた30年の結果を受け止め、事実に基づいた財政観に転換することが求められている。