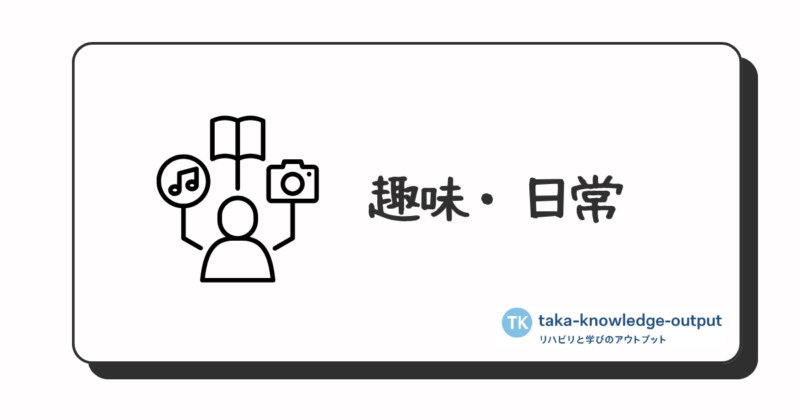科学と良心の狭間で問う──映画『ヒポクラテスの盲点』が映し出す“ワクチン後”の真実
映画批評:『ヒポクラテスの盲点』——科学と倫理のはざまで

新型コロナウイルスのパンデミックが世界を覆ってから数年。社会がようやく落ち着きを取り戻しつつある今、私たちはあの混乱の時期に何を見逃してきたのか。映画『ヒポクラテスの盲点』(監督:大西隼)は、その問いを静かに、しかし鋭く突きつける。
本作は、新型コロナワクチンの後遺症や健康被害の問題を、科学的データや医師たちの証言をもとに検証していくドキュメンタリーだ。特定の立場から断定するのではなく、賛否の二元論を超えて、「事実を正確に検証する必要性」を訴えている点に特徴がある。
■ “新薬”としてのmRNAワクチンをどう見るか
作品の中心にあるのは、「mRNAワクチン」という新技術の登場だ。従来のワクチンとは原理が異なり、わずか2年で開発・実用化されたというスピードは、医学史上前例がない。
京都大学名誉教授の福島雅典氏は、「通常10年かけるところを2年でつくったワクチンは本当に安全なのか」という問いを掲げる。これは単なる批判ではなく、科学者としての誠実な懐疑である。医療とは、人命を守るための行為であると同時に、常に不確実性と隣り合わせの営みである。そのジレンマを、映画は丁寧に映し出している。
■ 被害の“数字”の裏側にある人間の声
2025年2月時点で、厚生労働省が「接種後の死亡事例」として公表している件数は2261件。数値だけを見ると冷たい印象を受けるが、映画はその一つひとつの背後にある「個人の人生」を描き出す。
例えば、2回目接種の5日後に急死した28歳男性のケース。健康そのものだった青年の心臓が「溶けていた」という衝撃的な記録に、観客は言葉を失う。そこにセンセーショナルな演出はない。ただ、淡々と提示される事実が、私たちの「信頼してきたもの」を揺さぶる。
■ 医師たちの良心──「ワクチン問題研究会」の設立
映画では、医師や研究者たちが自らの信念に基づいて「ワクチン問題研究会」を立ち上げる様子も追う。医学的なデータの検証を求める彼らの活動は、決して反ワクチン運動ではない。むしろ、科学の健全性を守るための「問いかけ」であり、医療の信頼を取り戻すための試みである。
この姿勢は、タイトルにある“ヒポクラテス”──医の倫理を象徴する古代ギリシャの医師──の精神を想起させる。「まず害をなすなかれ」という誓いが、今もなお私たちに問いかけ続けている。
■ 社会全体が立ち止まるべき時期に
作品の終盤では、「日本では高齢者を中心に7回のブースター接種が推奨されてきたが、他国は2~3回が主流」というデータが示される。この差異は何を意味するのか。監督・大西隼は、答えを示すのではなく、観客自身に考えさせる構成をとる。
映画が訴えるのは、「今こそ立ち止まって検証しよう」という冷静なメッセージだ。感情的な主張ではなく、科学的・倫理的に再評価すること。それが、次のパンデミックに備えるための第一歩であると感じさせる。
■ 観る者に残る余韻
『ヒポクラテスの盲点』は、医学的知識を持たない一般の観客にも理解しやすい構成ながら、同時に医療従事者にとっても深く考えさせられる内容だ。映像は淡々としており、感情的な訴えよりも、事実を積み重ねていくスタイル。その静けさが、逆に強い余韻を残す。
私たちは、ワクチンを「希望の象徴」として受け入れた。しかしその光の裏側には、科学の限界や人間の傲慢さも潜んでいたのかもしれない。『ヒポクラテスの盲点』は、単なる“ワクチン映画”ではなく、医療と社会の関係性を根底から見つめ直す作品である。
■ まとめ
ドキュメンタリー映画『ヒポクラテスの盲点』は、医療の信頼、科学の検証、そして人間の良心という普遍的テーマを扱う。ワクチンの是非を問う前に、「何を知り、どう向き合うか」を考えさせる。
静かなトーンでありながら、観る者の心に深く刺さる一本だ。
一般の方はもちろんのこと、
医療従事者には非常に響く内容だと思えたおすすめの映画でした。