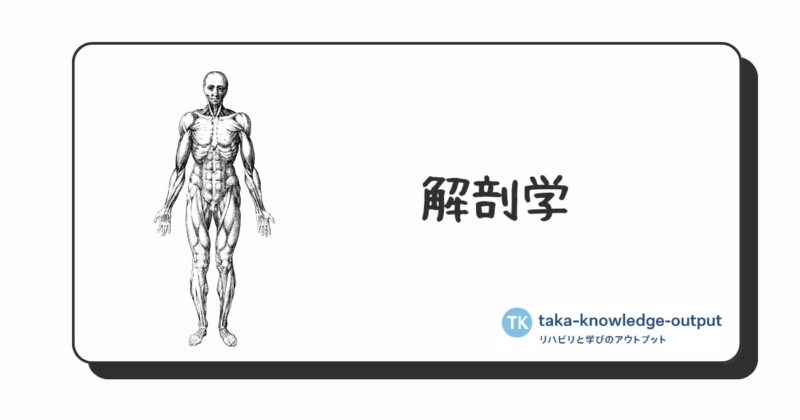炎症の基礎を理解する:急性から慢性までのメカニズム

炎症とは何か
炎症とは、損傷や感染に対して組織が示す免疫応答であり、自然免疫における重要な防御機構の一つです。炎症反応は分子と細胞が関わる複雑なシグナルのカスケードで進行し、結果として痛み・発赤・腫脹・熱感といった典型的な症状が現れます。
炎症は一見「悪いもの」と捉えられがちですが、実際には損傷の修復や病原体の排除に不可欠な生理反応です。ただし過剰または長期化すると、慢性炎症として病態に関与することになります。
急性炎症の特徴
急性炎症は、組織が損傷や感染に直面したときにまず起こる防御反応です。損傷部位の細胞はシグナル分子を放出し、次のような変化を誘導します。
- 血管拡張と血流増加:発赤や熱感の原因
- 血漿成分の滲出:腫脹を引き起こす
- 白血球の遊走:顆粒球、単球、リンパ球などが集まる
この過程で最初に出現するのが好中球です。好中球は病原体を貪食し、活性酸素種(ROS)や抗菌ペプチドを放出して殺菌します。しかしその作用は非選択的であり、周囲の正常組織にもダメージを与えることがあります。
さらに好中球はIL-1、IL-6、TNF-α、IFN-γといったサイトカインを放出し、全身性の炎症反応(発熱、白血球増加など)を引き起こします。急性炎症は通常、一時的な反応であり、原因が取り除かれると収束に向かいます。
慢性炎症のメカニズム
急性炎症が収まらず、長期にわたって持続すると慢性炎症へと移行します。その原因には、
- ウイルスや細菌の持続感染
- 花粉などの環境抗原
- 自己免疫反応
- 持続的な炎症性分子の活性化 などがあります。
慢性炎症では、好中球に代わって単球やマクロファージが中心的な役割を担います。血流から組織へ移行した単球はマクロファージに成熟し、病原体や老化細胞を貪食します。同時に、IL-1、TNF-α、プロスタグランジンなどの化学伝達物質を放出し、炎症を持続させます。
さらにTリンパ球やBリンパ球が関与し、特異的な免疫応答が加わります。Tリンパ球はウイルス感染細胞を破壊し、Bリンパ球は抗体を産生して病原体を排除します。こうした持続的反応は、組織にさらなるダメージを与える要因にもなります。
慢性炎症の結果
慢性炎症では、ROSやプロテアーゼが病原体だけでなく正常組織にも損傷を与えます。その結果、組織は線維性結合組織に置き換わり、瘢痕化が進行します。また、局所的な**血管新生(アンジオジェネシス)**が起こり、炎症の場が維持される特徴があります。
場合によっては炎症のカスケードが止まらず、組織修復が不完全なまま病態が進行することもあります。このような慢性的炎症は、さまざまな疾患に関連しています。
炎症と関連疾患
炎症は以下のような疾患に深く関与しています。
- 炎症性疾患:喘息、クローン病、関節リウマチ、腱炎、滑液包炎、胃炎、歯肉炎、炎症性腸疾患など
- 慢性疾患との関連:動脈硬化、肥満、糖尿病、アルツハイマー病、がん など
これらの疾患における炎症の役割や分子機構は現在も研究が進められており、今後の治療戦略の鍵となっています。
まとめ
炎症は損傷や感染から体を守る自然な防御機構である一方、その持続や慢性化はさまざまな疾患の要因となります。臨床家にとって炎症の仕組みを理解することは、治療方針を立てる上で欠かせません。急性と慢性の違いや、関与する細胞・分子の役割を把握することで、より適切な介入や患者教育につなげることができます。