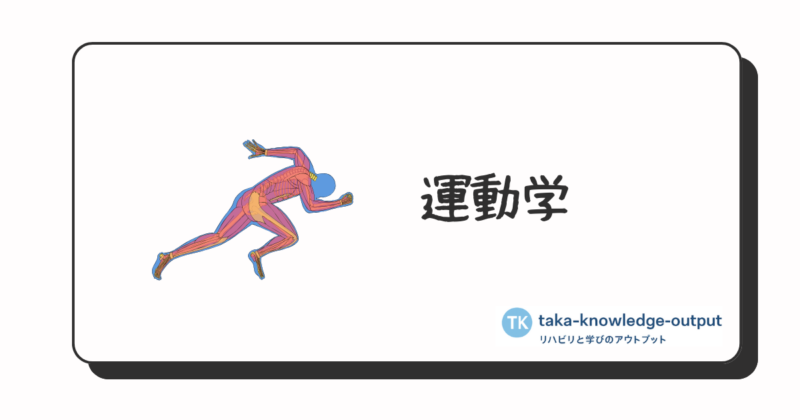歩行中に見える膝蓋下脂肪体の働きとは?―変形性膝関節症における新しい視点

歩行中に見える膝蓋下脂肪体の働きとは?―変形性膝関節症における新しい視点
膝の痛みや動きの制限を訴える患者を評価する際、多くの臨床家は関節軟骨や半月板、筋力に注目します。しかし近年、「膝蓋下脂肪体(infrapatellar fat pad:IFP)」の動きが膝関節機能や痛みの発現に深く関わっていることがわかってきました。
2024年に発表された広島大学の研究(Sugimotoら)では、歩行中のIFPの動きを動的超音波で解析し、変形性膝関節症(knee OA)患者と健常者を比較。その結果、膝OA群ではIFPの形状変化が著しく小さいことが明らかになりました。
■ IFPとは何か?
膝蓋下脂肪体(IFP)は、膝蓋腱と脛骨の間に位置する柔軟な脂肪組織です。歩行や膝の屈伸に伴い、形を変えて衝撃を吸収するクッションのような役割を果たしています。
しかし、膝OAではIFPに炎症・線維化・腫脹が起こりやすく、その柔軟性が失われることが報告されています。結果として、膝前面への局所的なストレスが増し、動作時の痛みを引き起こす可能性があると考えられています。
■ 研究の概要
研究では、膝OA患者12名、高齢健常者12名、若年健常者12名を対象に、歩行中のIFPの厚さの変化を超音波で測定。
さらに、3次元動作解析装置を用いて膝の角度や関節モーメントなどの運動学的・動力学的データも同時に取得しました。
- IFPの形状変化量(ΔIFP):
初期接地から最大厚までの差を指標とし、IFPの「動きの大きさ」を表します。
■ 主な結果
結果として、膝OA群のΔIFPは健常群に比べて有意に小さいことが示されました。
- OA群:1.4 ± 0.3 mm
- 高齢健常群:1.8 ± 0.2 mm
- 若年健常群:2.1 ± 0.5 mm
つまり、膝OA患者のIFPは歩行中に十分な形状変化が起きていないことが確認されました。
さらに、膝角度や歩行速度との関連は見られず、IFPの動的機能低下は「力学的要因」ではなく「組織の変性」による可能性が示唆されています。
■ 臨床的な示唆
この結果は、膝OAの痛みを「軟骨のすり減り」だけで説明するのでは不十分であることを示しています。
IFPが柔軟に形を変えられなくなると、衝撃吸収が不十分になり、膝蓋腱や滑膜、関節包にストレスが集中。結果として、歩行中に前膝部の痛みを引き起こす可能性が高まります。
臨床では、以下のような視点が役立つかもしれません。
- 前膝部痛を訴えるOA患者ではIFPの硬さや腫脹を観察する
- 超音波評価でIFPの可動性を確認する
- 膝蓋下脂肪体を意識した徒手療法や運動療法を取り入れる(例:大腿四頭筋リラクゼーション、膝蓋下圧の軽減など)
■ 老化との関係は?
興味深いことに、この研究では高齢者群と若年群でΔIFPに有意差がみられませんでした。つまり、IFPの動的変化は「加齢」ではなく「病変」によって制限されることが示唆されます。
加齢は膝OAのリスク要因であっても、直接的な原因ではないというこれまでの知見とも一致しています。IFPの動きを保つことが、変形性膝関節症の進行予防にもつながる可能性があります。
■ まとめ
- IFPは膝前面の衝撃を吸収する重要な組織である。
- 膝OA患者では、歩行中のIFPの形状変化が小さい。
- この「動的な柔軟性の低下」は、OA特有の痛みやストレス集中に関与する可能性がある。
- 今後、動的超音波によるIFP評価は、OAの早期発見や治療効果判定に有用な指標となるかもしれない。
歩行やスクワット時の痛みがなぜ起こるのか。その背景には「膝蓋下脂肪体の動き」という、これまで見落とされがちだった要素が隠れているかもしれません。
理学療法の現場でも、IFPの動的機能を意識したアプローチが今後ますます重要になっていくでしょう。