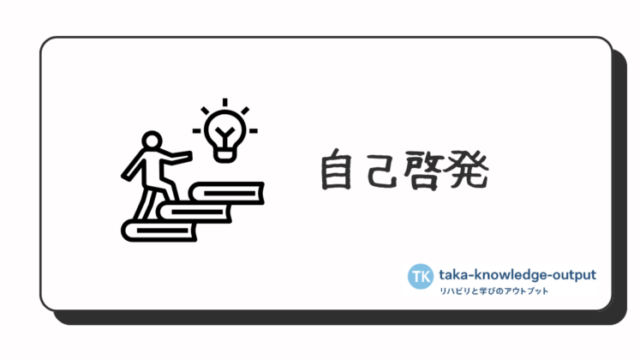「益税」は嘘だった?インボイス制度が隠す残酷な真実

「益税」という作られた幻影
裁判の結果が示す通り、消費税は「預かり金」ではなく、事業者が負担する「直接税」である。この前提に立てば、免税事業者が消費税をネコババしているという「益税」論がいかに的外れであるかが分かるはずだ。彼らは税を預かっているのではなく、単に市場価格で商品を売っているに過ぎない。 売上1000万円以下の事業者が免税とされているのは、特権があるからではない。「担税力」、すなわち税を負担する体力が不足しているからだ。年収103万円以下の人が所得税を免除されるのと同じく、これは零細事業者が生き残るための最低限のセーフティネットなのである。
赤字でも徴収される過酷な税
消費税の恐ろしさは、赤字であっても納税義務が生じる「外形標準課税」である点だ。これと同様の性質を持つ税に、大企業が支払う「事業税の付加価値割」がある。しかし、こちらは資本金1億円超の巨大企業のみが対象で、税率もわずか1.2%程度に過ぎない。 対して消費税は、売上1000万円を超えた時点で、その約8倍にあたる9%近い税率が課される。 本来、体力のある大企業にのみ許されるべき過酷な税制を、中小零細事業者にまで強いているのが消費税の実態なのだ。滞納額が国税の中で突出して多いのも、この無理な構造に原因があるといえる。
政府の二枚舌と罪悪感の利用
政府の説明は、その時々で都合よく変化してきた。導入時は「益税があるからお得だ」と飴を配り、裁判では「益税など存在しない」と開き直る。そして今、インボイス制度の導入にあたっては再び「益税は不公平だ」と主張し、免税事業者の罪悪感を煽っている。 「預かった税金を納めないのは悪いことだ」と思わせ、インボイス登録へと誘導する。しかし、そもそも預かってなどいないのだ。この制度の本質は、公平性の確保などではなく、立場の弱い者に対するさらなる搾取に他ならない。我々は「益税」という言葉の魔法から、目を覚ます必要があるだろう。