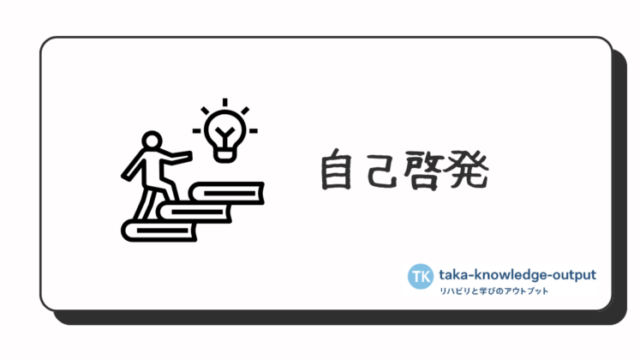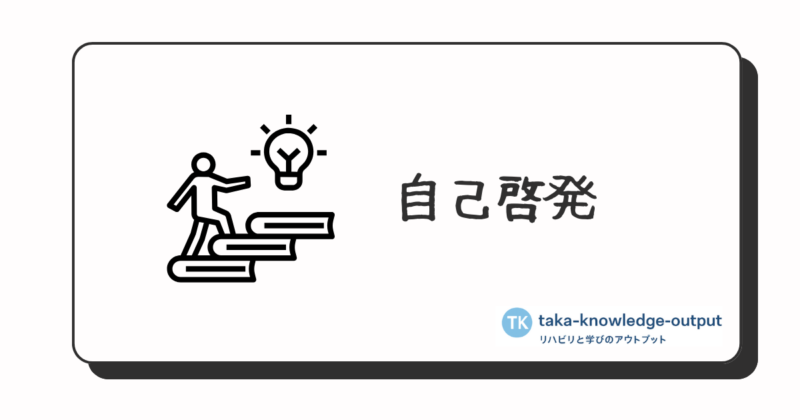老子が説く「言葉を超えた知恵」|語らずして知る、“玄同”という境地
言葉に頼ると、本当の「知」は止まる
老子はこう言います。
ものごとを知るには、言葉に頼るな。
言葉に頼って考えるときには、
知るという暗黙の働きが、止まってしまうからだ。
この言葉は、現代の私たちにとって衝撃的です。
なぜなら、私たちは“知ること=言語化すること”だと信じているからです。
しかし老子は、真の知とは「言葉にする前の静かな理解」だと言うのです。
それは、右手で右手を掴もうとしても掴めないようなもの。
知ろうとした瞬間に、その“知”は逃げてしまう。
老子が指摘するのは、「知」を追う心の動きそのものが、すでに「知らない状態」を作っているという逆説です。
「語らぬ知」とは、沈黙の中にある理解
私たちは、言葉で説明できないものを「理解できていない」と考えがちです。
けれども老子は、その真逆を説きます。
私たちは、ものごとを知らない間に、
暗黙のうちに、知ってしまっている。
たとえば──
- 美しい景色を見たときに感じる静かな感動。
- 赤ん坊を抱いたときの安心。
- 誰かの痛みを見て胸が痛む瞬間。
それらは説明できないけれど、確かに「知っている」こと。
この“言葉にならない理解”こそが、老子の言う「暗黙の知」です。
そして、それを無理に言葉にしようとすると、
その静かな感覚は崩れてしまう。
つまり、「知を語るほど、知から遠ざかる」。
これが老子の知恵の核心です。
「口を閉じ、光を和らげる」——知の静寂へ
老子は、真にものごとを知るための方法を次のように説きます。
ものごとを知るには、口を閉じて、言葉の門を閉じよう。
己の理知の光を和らげ、塵芥の類と同化する。
ここでいう「理知の光を和らげる」とは、
自分の知性や正しさを前に出さず、静かに観察するということ。
“自分が正しい”という光が強すぎると、
他者も、世界も、かえって見えなくなってしまう。
一歩引いて、
“分からないまま観る”
“判断せずに感じる”
そのとき初めて、世界の本当の姿が見えてくる。
それが老子の言う「玄同(げんどう)」——**“世界と一体化した知”**です。
「玄同」に至った人は、何ものにも揺るがない
老子はこの章の後半で、「玄同に至った人」のあり方を描きます。
このような知に至った者に対して、
言葉に頼って世界を認識する者は、対処のしようがない。
親しむこともできず、疎外することもできない。
利することもできず、害することもできない。
貴いとすることもできず、卑しいとすることもできない。
これはつまり、**「何者にも分類できない人」**のこと。
「玄同」に至った人は、
他人の評価や立場に左右されず、
誉められても驕らず、
貶されても動じない。
その人は、もはや「言葉の世界」から自由になっている。
だからこそ、他者はその人をコントロールできないのです。
老子は、そうした存在こそが「天下に尊ばれる」と結びます。
言葉を捨てて、沈黙の知を取り戻す
現代社会は、言葉にあふれています。
SNS、ニュース、会話、自己表現——すべてが「語ること」で満たされている。
けれども老子は、静かに問いかけます。
「あなたは、語る前の“知”を覚えているか?」
本当に大切なことは、言葉では伝えられない。
「愛」「平和」「美」「真理」——
それらは語るほどに遠のく。
だからこそ、時に口を閉じ、心を静め、世界の呼吸を聴くことが大切なのです。
まとめ|「玄同」とは、語らぬ知の完成
老子の第56章が伝えるのは、
「知る」ことは「語らない」ことでもあるという逆説的な真理です。
- 言葉に頼ると、真の理解は止まる。
- 沈黙の中で、ものごとは自然にわかる。
- 世界と一体になったとき、言葉はいらない。
老子は、言葉よりも“存在の知”を尊びました。
己の理知の光を和らげ、塵芥の類と同化する。
それは、偉大さを求めず、
ただ自然の一部として、静かに生きるということ。
語らずして知る人——
それが、老子のいう「玄同の人」なのです。