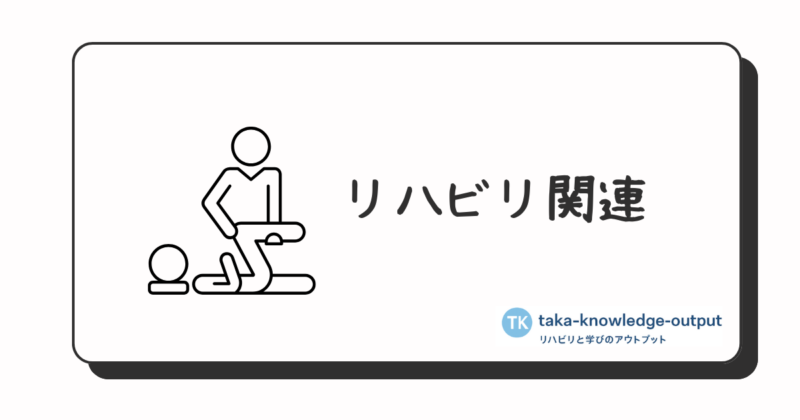半月板損傷と疼痛の関係を正しく理解する|理学的評価と超音波画像の連携が鍵

半月板損傷=痛みの原因ではない?
臨床で「半月板損傷」と診断された患者がすべて強い膝痛を訴えるわけではありません。
実際、画像上で明確な断裂が確認されても、疼痛を訴えないケースは多く報告されています。
その理由を理解するためには、半月板損傷による疼痛発生メカニズムを、構造的・力学的に捉える必要があります。
内側半月板損傷症例における疼痛の発生機序
膝関節を屈曲+内反+内旋方向に強制すると、
半月板外縁の断裂部が**離解(displacement)**し、同時に膝内側部に疼痛が出現しました。
一方で、膝関節を外反+外旋方向に強制した場合、
断裂部が**閉鎖(approximation)**し、疼痛は消失しています。
つまり、この症例では
「半月板外縁が離解方向に動いた時に疼痛が誘発される」
という、極めて明確な機械的疼痛パターンが認められました。
このことから、疼痛の主因は半月板内部そのものではなく、外縁部の神経終末を有する領域の刺激によるものであることが示唆されます。
半月板のどこが痛みを感じるのか?
前回の記事でも解説したように、
半月板の**外縁1/3(赤色部)**は血管および神経が分布している領域です。
この部位は関節包やMCL(内側側副靱帯)と線維的に連続しており、疼痛感受性が高い構造です。
一方、**中央〜内側1/3(白色部)**には神経も血管も存在しません。
したがって、MRIや超音波画像で白色部に断裂が確認されても、それ自体が疼痛を引き起こすことは基本的にありません。
この構造的特徴を踏まえると、
「画像上の断裂=疼痛源」ではない
という原則を常に念頭に置く必要があります。
超音波画像所見と理学所見をリンクさせる重要性
超音波画像は半月板損傷の形態や滑走状態を把握する上で非常に有用ですが、
それだけで疼痛の有無や原因を断定することはできません。
今回の症例のように、
- 屈曲+内旋で疼痛出現
- 外旋で疼痛軽減
という明確な運動方向依存性がある場合、疼痛は構造損傷そのものではなく、力学的ストレスによる神経刺激によって生じていると考えられます。
したがって、画像評価と理学所見を統合して考えることが極めて重要です。
画像で確認できる“損傷部”があっても、それが疼痛源とは限らない。
逆に、画像に異常がなくても、動的ストレスで外縁部が過伸張されれば痛みは出現します。
理学療法の考え方:疼痛方向の制動と荷重制御
疼痛や不安定性が明確な方向(この症例では内反・内旋方向)に生じる場合、
その動きを**制動(stabilize)**することが治療戦略の基本となります。
1. 靱帯ストレッチ療法の活用
内側構造(MCL・関節包)の柔軟性低下があると、半月板外縁の動きが制限され、
離解時のストレスが過大になります。
そこで、疼痛を誘発しない範囲での靱帯ストレッチ療法により、関節包・靱帯の滑走性を改善させることが有効です。
2. 動的制動を促す運動療法
内旋方向で疼痛を呈する症例では、外旋筋群(特に大腿二頭筋や外側広筋)の機能強化が、
動的制動に寄与します。
膝周囲筋のバランス改善によって、関節内の力学的ストレスを緩和できます。
3. インソールによるアライメント調整
膝の内反ストレスが繰り返されると、半月板外縁への圧縮・牽引力が増加します。
そのため、外側ウェッジ型インソールによる荷重ラインの調整が有効です。
下肢全体の力学的アライメントを再構築することで、半月板外縁へのストレス軽減が期待できます。
まとめ:疼痛の“場所”ではなく、“動き”を診る
半月板損傷において、疼痛の有無を決めるのは「どこが損傷しているか」ではなく、
「どの方向の運動でストレスが集中するか」という力学的視点です。
- 画像で損傷が見えても、それが疼痛源とは限らない
- 外縁部(赤色部)の神経終末が疼痛の主な発生源
- 理学所見と画像所見を組み合わせて病態を捉える
この3つを理解しておくことで、半月板損傷患者への治療はより精密になります。
疼痛方向を制動し、組織の滑走性と荷重分散を改善することこそ、理学療法士の臨床的アプローチの核心といえるでしょう。