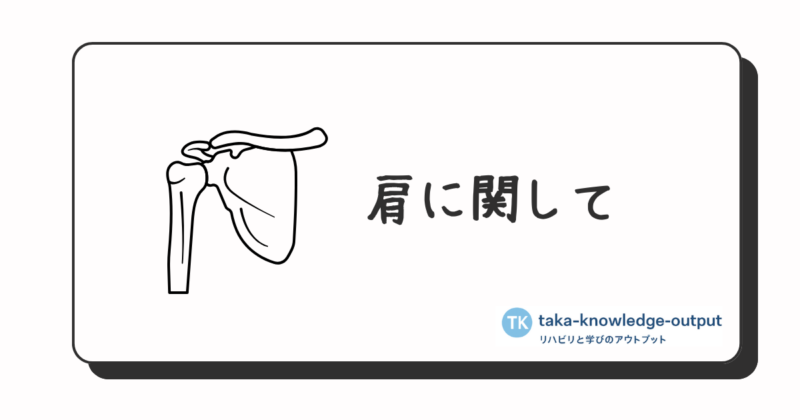半月板周辺の血管分布を理解する|修復可能性と疼痛発生のメカニズムを解説

半月板の形態と機能的意義
半月板(meniscus)は、膝関節内でC字状の線維軟骨構造を持つ重要な組織です。大腿骨と脛骨の間でクッションのような役割を果たし、衝撃吸収・荷重分散・関節安定化といった多面的な機能を担っています。
形態的には、外側半月板はややO字状、内側半月板はよりC字状を呈します。この形態の違いが、膝関節の運動軌跡に適応しており、動的安定性を支える基盤となっています。
しかし、この半月板の「修復可能性」や「疼痛発生」において最も重要なのが、血管分布です。
半月板の血管分布:外縁1/3の“赤色部”と無血管領域
半月板の血流は、周囲の滑膜血管網から供給されています。
特に、半月板の**外縁1/3(red zone)**には、関節包や被膜から進入する毛細血管が豊富に分布しており、血流が存在する領域です。
研究的には、この部位に血液の希釈枝を注入すると、外縁部に限局して血管染色が確認されることが知られています(C22b)。
この事実は、外縁1/3が生理的に血流を保ち、修復反応に対応できる領域であることを意味します。
一方、半月板の**中央〜内側1/3(white zone)**には血管も神経もほとんど存在しません。
この領域の細胞は主に拡散によって栄養を受け取っており、外傷や断裂が生じても自己修復能力が非常に乏しいのが特徴です。
“赤色部”が持つ修復ポテンシャル
半月板外縁の赤色部は、関節包や靱帯と癒合しており、これらの結合組織を介して血管・線維芽細胞・炎症性細胞が流入します。
そのため、外縁1/3の損傷であれば、保存療法や縫合術によって自然修復が期待できるケースも少なくありません。
また、この血管領域では、組織損傷時に炎症性サイトカインの局所放出が起こり、線維化・コラーゲン再生などの反応が誘導されます。
これは、いわば「修復反応のスイッチ」が入る領域であるともいえます。
臨床上、「半月板のどの位置で損傷しているか」を評価することは、手術適応の判断や予後予測に直結します。
MRIや関節鏡で赤色部損傷が確認された場合、再縫合・保存治療の選択肢を検討する意義があります。
“白色部”損傷では疼痛が起こらない理由
半月板中央〜内側の白色部(無血管領域)には、血管だけでなく神経終末も存在しません。
そのため、白色部での裂離や断裂が起きても、疼痛を感じにくいことが臨床的に知られています。
一方で、疼痛が出現するケースの多くは、外縁1/3(赤色部)や関節包との連結部でのストレスが関与します。
ここには神経線維が分布しており、関節包や靱帯と連続しているため、引っかかりやインピンジメントが生じると疼痛刺激が発生します。
つまり、痛みの有無=血流・神経の存在領域の違いを反映しているのです。
半月板損傷と疼痛の臨床的メカニズム
臨床現場でよく遭遇する半月板関連痛の多くは、以下のようなメカニズムで発生します。
- 外縁部の過剰な牽引・圧迫ストレス
→ 靱帯・関節包の緊張による疼痛誘発 - 関節包癒合部での微細断裂
→ 局所的炎症と滑膜反応の活性化 - 半月板の動的インピンジメント
→ 関節内での挟み込みや“引っかかり感”
これらはすべて、血管・神経が存在する赤色部領域での現象であり、したがって疼痛を伴いやすいのです。
逆に、白色部損傷では断裂そのものは大きくても、痛みを訴えないことが多く、機能障害よりも機械的障害(ロッキングなど)で気づかれることが一般的です。
まとめ:血管分布を知ることは治療戦略の第一歩
半月板の血管分布を理解することは、単なる解剖知識にとどまらず、修復可能性の判断・疼痛メカニズムの理解・治療選択の基盤となります。
- 外縁1/3(赤色部):血流あり、修復・疼痛あり
- 中央〜内側1/3(白色部):無血管・無神経、疼痛なし
この基本構造を踏まえることで、理学療法士は損傷位置に応じたリハビリ方針を立てることができます。
とくに術後リハビリでは、血流を保ちつつストレスを最小限にする屈伸角度や荷重制限の設定が鍵となります。
半月板損傷の評価・治療を行う際には、ぜひこの「血管分布と疼痛発生の関係」を意識して臨床に活かしてみてください。