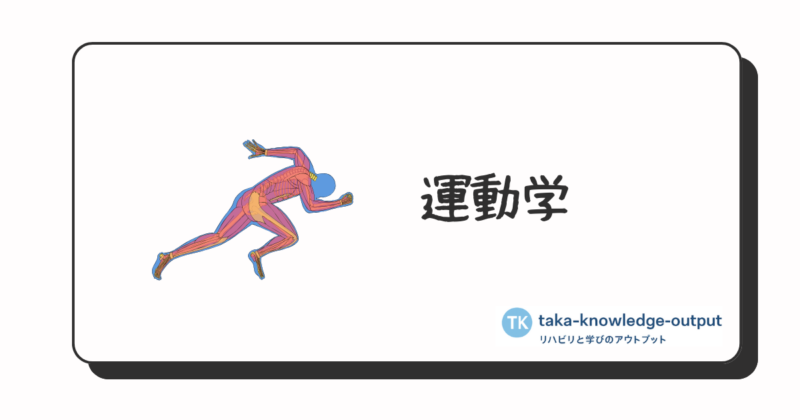筋力トレーニングの効果は3つに分類できる
筋力トレーニングの効果は以下の3つに整理されます。
- 運動単位の動員数増加(筋力向上)
- 筋肥大(筋断面積の増加)
- 筋線維の酸素供給能力の向上(筋持久力の向上)
臨床では「筋力低下」と見えるケースでも、実際には疼痛・関節水腫・不安定性・運動パターンの偏りなどが原因で筋出力が発揮できていない場合があります。この場合、単純に筋トレを処方しても改善は難しく、原因評価が不可欠です。
筋力を決める要因:運動単位と筋断面積
筋力は「参加する運動単位数」と「筋断面積」の2つによって決まります。
- 運動単位:1つの運動ニューロンと、それに支配される筋線維群。高負荷運動では多くの運動単位が動員され、短期間で筋力向上が期待できます。
- 筋肥大:起こるのは白筋線維(速筋線維)のみ。白筋の割合が多い筋ほど肥大しやすい特性があります。
筋肥大の条件:負荷と回数
筋肥大には 1RM(1回だけ持ち上げられる重量)の65%以上 の負荷が必要です。
- 例:10kgを4回まで上げられる場合 → 4RM(=1RMの約90%)
- 推奨範囲:65〜90%1RMで5〜15回の反復
- 高負荷(90%以上)は反復困難、65%未満では持久力向上が主体
筋肥大には「量の確保」が必要であり、筋を低酸素状態に追い込むことが重要です。
筋サテライト細胞の役割
筋トレで筋線維が損傷すると「救援信号」が発せられます。これを感知した 筋サテライト細胞 が集まり、損傷部位に融合して補修を行います。
- 修復時に「壊れた分よりやや多め」に補修
- 結果:筋線維が太くなり、筋肥大につながる
加圧トレーニング:低負荷で筋肥大を起こす方法
加圧トレーニングは、筋肉を人工的に低酸素状態に追い込むことで筋肥大を促す方法です。
- 方法:上腕や大腿の基部を専用ベルトで加圧
→ 動脈流はある程度維持し、静脈流を制限
- 効果:40%1RM程度の低負荷でも筋肥大が可能
- 通常では50%以下では筋肥大が起こらないため、非常に効率的
注意点
- 高負荷では筋収縮のポンプ作用で血流が流れ、効果が減弱
- 目的は「高負荷の錯覚」を筋に与え、サテライト細胞を動員すること
ノンロック法:器具がなくてもできる代替法
加圧ベルトがなくても、**関節を完全伸展・屈曲させない「ノンロック」**で低酸素環境を作ることができます。
- スクワット例
膝を伸ばしきらず、やや曲げた位置までで反復
→ 常に収縮状態を維持し、血流が制限される
→ 筋肉は「強負荷がかかっている」と錯覚する
負荷の目安
- 5〜10回で下肢にだるさを感じる程度
- 正しく実施できていれば「熱く張るような感覚」と適度な疲労感が得られる
👉 メリット:高負荷を使わないため、翌日の強い筋肉痛や障害リスクを軽減できる
まとめ
- 筋力トレーニングの効果は「運動単位動員・筋肥大・酸素供給力向上」
- 筋肥大には1RM65%以上の負荷と反復量の確保が必要
- サテライト細胞が筋修復を担い、肥大を引き起こす
- 加圧トレーニングは低負荷でも筋肥大を可能にする効率的手段
- ノンロック法は道具不要で低酸素環境を作れる実践的代替法
臨床では「なぜ筋出力が落ちているのか」を正しく評価し、適切な負荷と方法を選択することが重要です。単に「鍛える」だけではなく、科学的根拠に基づいた筋力トレーニングを組み込むことで、より効果的なリハビリを実現できます。
ABOUT ME

理学療法士として臨床に携わりながら、リハビリ・運動学・生理学を中心に学びを整理し発信しています。心理学や自己啓発、読書からの気づきも取り入れ、専門職だけでなく一般の方にも役立つ知識を届けることを目指しています。