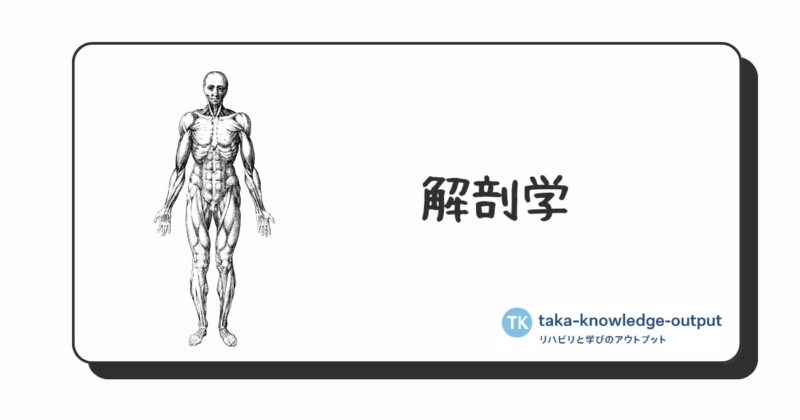筋緊張が増大する原因と臨床でのアプローチ:支持・過用・防御・癒着を中心に

筋緊張の増大は臨床で避けて通れない問題
リハビリテーションにおいて、患者の「痛み」や「こり」に関与する大きな因子が 筋緊張の増大 です。筋緊張は本来、姿勢保持や運動制御のために必要ですが、過度に高まると疼痛や可動域制限を引き起こします。臨床では、以下の4つが特に頻繁に観察される要因です。
1. 支持(Support)
身体の変位を補正するために筋緊張が高まるケースです。
- 例:頭部前方位 → 僧帽筋上部線維の持続的緊張
- 臨床的特徴:不良姿勢が続くことで筋持久力が低下し、慢性疼痛の原因となる
👉 アプローチ:姿勢修正、頸部・肩甲帯の筋バランス改善エクササイズ
2. 過用(Overuse)
特定の筋を繰り返し使用することで緊張が高まる状態です。
- 例:テニス肘(外側上顆炎)における前腕伸筋群の過用
- 臨床的特徴:局所の筋疲労や微細損傷による慢性炎症
👉 アプローチ:使用頻度の調整、ストレッチ、エキセントリックトレーニング
3. 防御(Guarding)
痛みを回避するために周囲の筋が防御的に収縮している状態です。
- 例:五十肩における腱板筋群の緊張増大
- 臨床的特徴:可動域が制限され、さらに動かさないことが二次的拘縮を助長
👉 アプローチ:疼痛コントロール、段階的な関節可動域練習
4. 癒着(Adhesion)
外傷や炎症後に筋膜などの結合組織が癒着し、滑走不全を起こした状態です。
- 例:足関節捻挫後の瘢痕形成による可動制限
- 臨床的特徴:伸張や収縮の際に引っ張られるような痛み
👉 アプローチ:徒手療法(ファシアリリース)、摩擦マッサージ
ミネラルバランスと筋緊張
筋緊張には栄養学的因子も関与します。特に カルシウム(Ca)とマグネシウム(Mg) は重要です。
- Ca:筋収縮に関与
- Mg:筋弛緩に関与
運動による発汗でMgは失われやすく、不足すると筋収縮が過剰になり、痙攣やこむら返りを引き起こします。
👉 臨床的示唆:筋・筋膜性疼痛の患者には、治療後に水分・ミネラル補給を促すことが望ましい。
神経生理学的観点:α運動ニューロンの制御
筋緊張は α運動ニューロンの発火状態 に依存します。これを抑制する方法として次の2つが挙げられます。
- 錘内筋の触圧覚(Ⅱ線維)の刺激
- 腱受容器(Ⅰb線維)の刺激
これらの入力は反射的にα運動ニューロンを抑制し、筋緊張を低下させます。
錐体外路系の働きにより、私たちは無意識に適度な緊張を維持していますが、このバランスが崩れると過緊張が発生します。
筋膜の特性とアプローチ
ファシアの主成分である コラーゲンやエラスチン は「架橋結合」によって組織強度を保っています。しかし結合が強くなると滑走不全を起こし、疼痛や可動域制限を生じます。
- 性質:加熱で軟化・流動化、冷却で硬化
- 臨床応用:摩擦を加えて局所に熱を持たせると滑走性が改善する
👉 実践ポイント
- 摩擦マッサージは少なくとも2分以上持続
- 圧を加えながら組織を温め、結合を軟化させる
まとめ
- 筋緊張の主な原因は「支持」「過用」「防御」「癒着」の4つ
- ミネラルバランス(Ca・Mg)が崩れると痙攣やこむら返りを助長する
- 筋緊張はα運動ニューロンの発火に依存し、感覚入力で抑制可能
- ファシアは加熱で滑走性が改善し、摩擦マッサージが有効
筋緊張は単なる「こり」ではなく、多因子が関与する現象です。評価とアプローチの両面で知識を活かすことで、より効果的な疼痛改善と機能回復が可能となります。