整形疾患のリハビリアプローチ:疼痛評価から組織リリースまでの実践的視点
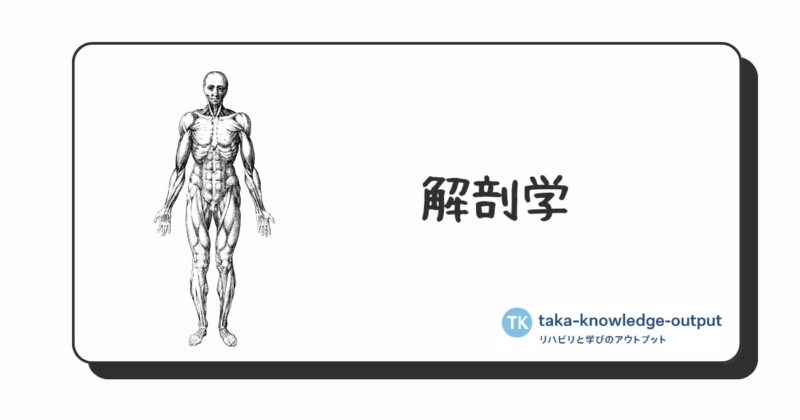
整形疾患リハビリの核心は「臨床推論」
整形疾患に対するリハビリテーションは、臨床推論の繰り返しによって成り立っています。患者が訴える「痛み」がどこから発生しているのかを見極めることが、治療の第一歩であり、最重要課題です。
特に以下の3点を押さえる必要があります。
- 疼痛誘発組織は何か
- 疼痛に至った原因は何か
- 今後どのような経過をたどるか
この推論を誤れば、以後の治療プログラムも全て誤った方向に進んでしまいます。つまり、治療は臨床推論の延長線上にあるという理解が不可欠です。
整形疾患で用いる代表的アプローチ
整形疾患のリハビリでは、以下の6つのアプローチが頻繁に用いられます。
A. 組織リリース
B. 筋ストレッチング
C. 関節モビライゼーション
D. 運動パターンの促通
E. 筋力トレーニング
F. 患者教育
このうち A~Cは「拘縮の改善」、D~Fは「負荷の軽減」 を主な目的としています。
① 組織リリース
「組織リリース」という言葉は一般に「マッサージ」と混同されがちですが、大きな違いは どの組織に対してアプローチしているのかを明確化している点 です。
対象となるのは主に 筋 と 筋膜(ファシア) です。それぞれリリース時の反応は異なります。
- 筋過緊張に対するリリース
血流が改善され、発痛物質が流れ出すことで「イタ気持ちいい」と表現されることが多い。 - 癒着したファシアに対するリリース
強い痛みとして訴えるケースが多い。特に深筋膜は神経が豊富なため、痛みが強く出やすい。
組織リリースの理論的背景
組織リリース時には触圧覚が刺激され、ゲートコントロール理論による鎮痛効果が期待できます。
- 末梢からの別刺激によって侵害刺激を変化させる
- 中枢での感情・認知的要素によって侵害刺激を調整する
👉 臨床例
経皮的電気神経刺激(TENS)はこの理論を応用したもので、Aβ線維を刺激して痛みを抑制しています。
ヤンダの知見:硬くなりやすい筋と弱くなりやすい筋
リハビリテーション領域に大きな影響を与えたヤンダ医師は、疾患や病態ごとに硬くなりやすい筋と弱くなりやすい筋には一定の傾向があることを報告しました。
- 脳卒中:麻痺しやすい筋
- 脳性麻痺:痙性が生じやすい筋
- 筋骨格系疾患:硬くなりやすい筋・弱くなりやすい筋が特定のパターンを示す
斜角筋の特徴
特に斜角筋は「硬くなりやすい」「弱くもなりやすい」という両面性を持ち、異常をきたしやすい筋肉として報告されています。臨床で問題の原因となる頻度が高く、評価の際には注意が必要です。
まとめ:推論からアプローチへ
- 整形疾患リハビリの第一歩は「疼痛誘発組織の同定」
- 臨床推論が誤れば治療全体が無効化される
- アプローチは「拘縮の改善(組織リリース・ストレッチ・モビライゼーション)」と「負荷軽減(運動促通・筋力強化・教育)」に整理できる
- 組織リリースはゲートコントロール理論を背景に、筋と筋膜に対して異なる効果を示す
- ヤンダの知見は筋の評価と治療選択の指標となる
整形疾患のリハビリは「勘」ではなく「推論」に基づくべきです。評価からアプローチまでの一連のプロセスを論理的に積み上げていくことが、最適な治療効果につながります。


