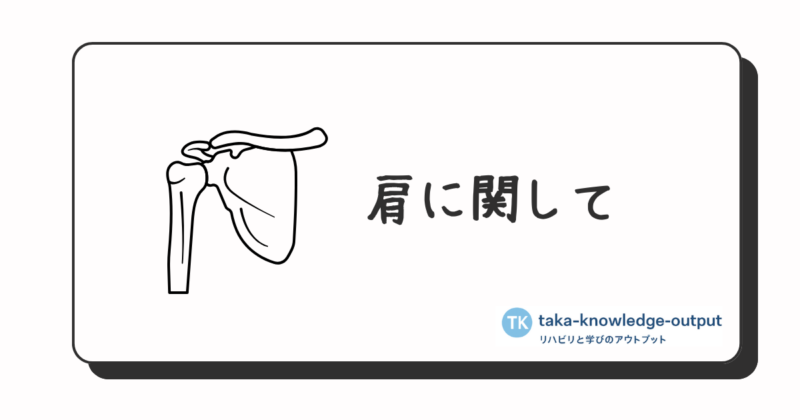鵞足部の解剖と機能的意義を徹底解説|縫工筋・薄筋・半腱様筋の協調と膝安定性の関係

鵞足部とは?3筋の協調が生み出す膝内側の安定構造
鵞足部(pes anserinus)は、膝関節の内側に位置し、**縫工筋(sartorius muscle)・薄筋(gracilis muscle)・半腱様筋(semitendinosus muscle)**の3つの筋腱が脛骨内側に扇状に付着する部位です。
その形状が「ガチョウの足(goose foot)」に似ていることから、この名称がつけられました(C28)。
この3筋は、それぞれ異なる起始部を持ちながら、最終的に共通の脛骨内側上部へと集束します。
前方から順に、
- 縫工筋(表層)
- 薄筋(中間層)
- 半腱様筋(深層)
の順に配列しており、各筋腱が層構造を形成することで、動的安定性と滑走性を両立しています。
鵞足部の構造と滑液包の存在
鵞足部は膝内側から脛骨内側面に広がっており、その下には鵞足滑液包(pes anserine bursa)が存在します。
この滑液包は、主に半腱様筋腱と脛骨骨膜の間に形成され、膝の屈伸運動時に生じる摩擦を軽減する役割を果たしています。
しかし、過度な膝屈曲動作や下腿の外旋動作が繰り返されると、この滑液包に炎症が起き、**鵞足炎(pes anserine bursitis)**を発症します。
臨床では、膝内側のすね付近に限局した圧痛や腫脹、階段昇降時の疼痛などが特徴的な症状として見られます。
鵞足部と下腿筋膜の関係
鵞足部の後内側には、**下腿筋膜(crural fascia)**が膝関節を覆うように存在しています。
薄筋や半腱様筋はこの筋膜と線維的に連結しており、下腿筋膜の緊張状態がこれらの筋腱の張力に直接影響します。
例えば、足関節背屈時には下腿筋膜が牽引され、結果的に薄筋・半腱様筋腱の付着部にも張力が伝達されます。
このように、足部—下腿—膝関節は筋膜連結を介して一体的に働いており、鵞足部はその“張力伝達ハブ”のような機能を持っています。
鵞足部の線維構造と付着形態
図C28では、鵞足部の詳細な線維構造が示されています。
以下のような層構造を理解することで、滑走障害や疼痛の病態をより正確に捉えることができます。
- 表層の縦軸線維束:縫工筋腱が主体。膝伸展時に主動的に緊張し、前内側方向の安定性を補強。
- 深層の横軸線維束:半腱様筋腱が主体。屈曲時に膝後内側の安定性を担う。
- 薄筋腱(主腱)と薄筋腱盤(副腱):主腱は縦走し、副腱は筋膜様に広がる。滑走性に寄与。
- 半腱様筋腱(主腱)と半腱様筋腱盤(副腱):副腱が広く脛骨内側面に広がり、MCL(内側側副靱帯)と部分的に癒合。
- 下腿筋膜との連結:膝の動作に応じて張力伝達を行う。
このように、鵞足部は単なる3筋の集合ではなく、多層的な腱構造と筋膜連結をもつ複合体として理解することが重要です。
鵞足部の機能的役割:膝安定化の要
鵞足部は、膝関節の内側安定性において**動的な靭帯機構(dynamic ligamentous structure)**として機能します。
立位伸展位では、下腿が前傾しながら関節包を前内側方向に張る構造になっており、
鵞足筋群が収縮することで、膝内側関節包が前方に引き寄せられ、内反・回旋ストレスを制御します。
さらに、鵞足部の腱線維はAOL(Anterior Oblique Ligament)と交差するように走行しており、
膝伸展位でのMCLと協調的な安定作用を示します。
この協働関係により、膝内側部の過伸展や過外旋を防ぐ“補助的靭帯”として働いているのです。
臨床的視点:鵞足部由来の痛みをどう評価するか
鵞足部の痛み(鵞足炎など)は、
- 過剰な膝屈曲や外旋運動
- 下腿筋膜の緊張増加
- 股関節内旋制限による代償動作
などによって誘発されます。
評価の際は、
- 膝軽度屈曲位での内側脛骨部圧痛
- 膝屈曲抵抗時の疼痛出現
- 足関節背屈による付着部の牽引痛
を確認することで、鵞足部由来の痛みを鑑別できます。
また、エコー観察では滑液包の腫脹や筋腱付着部の肥厚が描出されるため、滑走障害の有無を動的に確認することが推奨されます。
まとめ:鵞足部は「筋」と「靭帯」をつなぐハイブリッド構造
鵞足部は、縫工筋・薄筋・半腱様筋という3つの筋腱が重なり合う複合構造であり、
単なる屈曲筋群の集合ではなく、膝内側を安定化させる動的靭帯装置として機能しています。
- 多層的な線維構造と滑液包
- 下腿筋膜との張力連結
- AOLやMCLとの協調的安定化機構
これらを理解することで、膝内側痛や鵞足炎などの病態をより正確に評価し、
効果的な治療・運動療法につなげることができます。