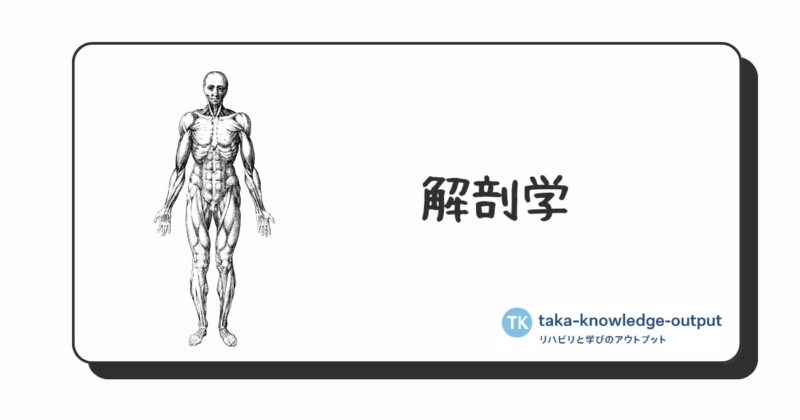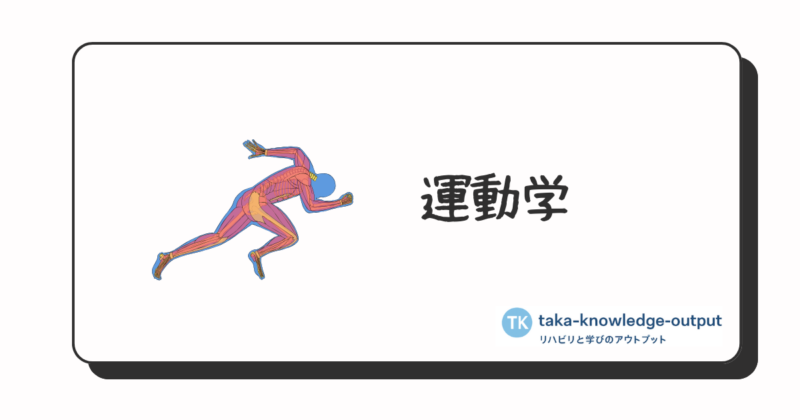鵞足腱障害の発症機序を解説|若年スポーツ例と膝OA例で異なる力学的背景

鵞足腱障害とは? ― 膝内側の“過使用”から始まる痛み
鵞足部(pes anserinus)は、縫工筋・薄筋・半腱様筋の3つの筋腱が脛骨内側上部に集合する部位で、膝関節内側の動的安定性を支える重要な構造です。
これらの筋は膝関節の過外旋(external rotation)を制御する役割を持ち、歩行・ランニング・ジャンプなどの動作で常に働いています。
鵞足腱障害(pes anserine tendinopathy)は、これらの筋腱群のオーバーユース(過使用)や摩擦刺激によって生じる炎症性疾患であり、
- 若年スポーツ選手
- 高齢の変形性膝関節症(OA)患者
に二峰性に好発することが知られています。
発症機序①:スポーツ(若年者)における鵞足腱障害
スポーツ活動中に発症する鵞足炎の多くは、**股関節内旋位+膝関節外旋位(knee-in toe-out)**というマルアライメントを呈しています。
特にランナーやジャンパーなど、反復的な膝屈伸動作を繰り返す競技者に多く見られます。
この動作パターンでは、
- 膝関節外旋によって鵞足腱が伸張・摩擦ストレスを受けやすくなる
- 股関節内旋により大腿内転筋群の出力が低下し、鵞足筋群の代償的収縮が増加
- 膝屈曲動作時にMCLとの滑走抵抗が増加
結果として、鵞足腱に**低収縮状態での反復的摩擦(friction stress)**が加わり、腱膜部に微小損傷が蓄積します。
これが局所炎症へと進展し、疼痛を呈するようになります。
▶ スポーツ例の臨床的特徴
- 若年者・アスリートに多い
- ランニングやジャンプで痛みが出る
- 動作中に膝内側に「張る」「引っかかる」感覚
- 鵞足部の局所圧痛+屈伸時摩擦音を認める
このタイプの鵞足炎は、いわば“動的摩擦型”の病態といえます。
発症機序②:膝OA(高齢者)における鵞足腱障害
変形性膝関節症(knee OA)を背景に発症する鵞足腱障害では、
**股関節外旋位+膝関節外旋位(knee-out toe-in)**という異なるマルアライメントが特徴的です。
OA例では、
- 大腿骨の外旋と下腿の内旋により、膝関節内側が閉鎖方向へ偏位
- 荷重時に膝内側の圧縮ストレスが増加
- 鵞足筋群(特に薄筋・半腱様筋)に過剰な収縮負荷がかかる
結果として、膝内側において鵞足腱の持続的緊張・短縮が発生します。
これが屈曲動作や荷重時に摩擦力を高め、慢性的な炎症・疼痛へとつながります。
▶ 膝OA例の臨床的特徴
- 中高年〜高齢者に多い
- 歩行時・立ち上がり時の膝内側痛
- 鵞足部の圧痛・腫脹・熱感
- 股関節外旋筋の代償的過緊張
この病態は、**「支持期における過収縮型鵞足炎」**と表現でき、
関節変形に伴う筋-腱膜の過緊張が痛みの背景にあります。
鵞足腱障害の共通病態:オーバーユースと滑走不全
スポーツ例・OA例に共通して、鵞足腱障害の根底にあるのはオーバーユース(overuse)です。
鵞足筋群の常時短縮・持続収縮状態が続くことで、次のようなメカニズムで炎症が発生します。
- 屈曲運動に伴う摩擦(friction)
→ 鵞足腱とMCLの間で繰り返し擦れが生じる。 - 牽引力(traction force)の増加
→ 腱付着部に機械的刺激が蓄積。 - 滑液包(鵞足包)の反応性肥厚
→ 摩擦・熱刺激により滑走がさらに悪化。 - 過屈曲位でのストレス集中
→ 半腱様筋や薄筋が強く引かれ、局所微小損傷が進展。
この一連の過程を経て、鵞足腱障害 → 鵞足炎 → 慢性化・滑走不全という病態が形成されていきます(C32)。
臨床での評価・介入の方向性
鵞足腱障害の治療を考える上では、発症メカニズムに応じたアライメント評価と動作再教育が必須です。
① スポーツ例(動的摩擦型)
- 股関節外旋筋群(深層外旋六筋)の再教育
- 膝外旋のコントロール強化
- ランニング動作での膝の過内旋・外旋の修正
② 膝OA例(過収縮型)
- 股関節内旋筋群(中殿筋前部・大腿筋膜張筋)の活性化
- 鵞足筋群のストレッチ+滑走モビライゼーション
- 荷重線の正中化を目的としたインソール調整
共通して、足関節背屈位での動的伸張ストレッチは、下腿筋膜と鵞足腱膜の滑走を促進し、有効なアプローチです。
まとめ:鵞足腱障害は「アライメント」と「オーバーユース」の相互作用
鵞足腱障害は、
- スポーツ例では「摩擦による動的刺激」
- OA例では「過収縮による静的刺激」
という異なる力学的要因から発症します。
共通するのは、鵞足筋群の過使用と滑走不全。
屈曲運動に伴う摩擦・牽引ストレスが腱付着部の微小損傷を繰り返し、炎症を引き起こします。
臨床家は「膝内側の痛み」を単なる炎症として捉えるのではなく、
股関節・膝・足関節の運動連鎖の中で生じるオーバーユース現象として捉える視点が求められます。
この理解が、再発を防ぎ、より持続的な疼痛改善へと導く鍵となるでしょう。