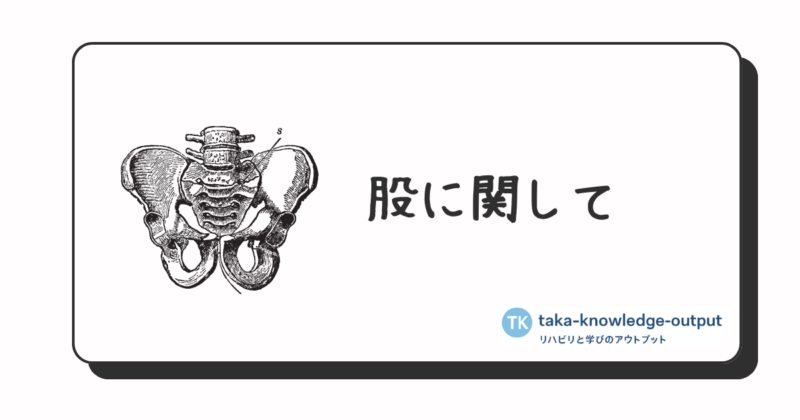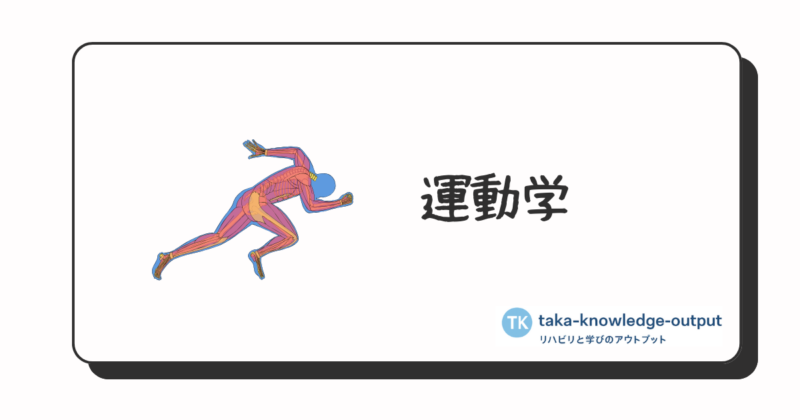膝窩筋腱溝と膝窩筋腱の機能解剖:膝屈曲角度による安定化メカニズムを理解する

はじめに
膝窩筋(popliteus muscle)は、膝関節後外側の深層に位置し、膝外側支持機構の一部として回旋安定性を担う筋です。
特に、膝窩筋腱が走行する「膝窩筋腱溝(popliteus tendon groove)」は、膝関節屈曲・伸展に伴う腱の動態を制御する重要な構造です。
本記事では、膝窩筋腱と腱溝の解剖学的特徴、膝屈曲角度による安定化メカニズム、そして臨床応用について整理します。
膝窩筋腱溝の解剖
膝窩筋腱溝は、大腿骨外側顆の後方に形成された骨性の溝(bony groove)であり、膝窩筋腱が通過する経路となります。
この溝は、外側側副靭帯(LCL)の深層に位置しており、LCLが「橋のように」腱の上を跨ぐ形で配置されています。
LCLは、
- LCL-femur:大腿骨外側上顆に付着
- LCL-fibula:腓骨頭に付着
と、両端を結ぶように張力構造を形成しており、膝外側の静的安定性を担います。
そのすぐ下層を走行する膝窩筋腱は、このLCLに対して深層を滑走しながら大腿骨外側顆後面へ付着します。
この付着部は「PLT(popliteus tendon attachment)」と呼ばれ、膝関節の屈伸運動に応じて腱の滑走経路が変化します。
膝窩筋腱と膝屈曲角度の関係
膝窩筋腱は、膝関節の屈曲角度に応じて膝窩筋腱溝に“はまり込む”か否かが変化します。
- 膝関節伸展位
膝窩筋腱は溝から外れており、自由度の高い滑走状態にあります。
このとき、膝窩筋は比較的リラックスし、膝の伸展運動を妨げることはありません。 - 膝関節屈曲が進行(約112°)
膝窩筋腱が骨溝内に**完全に収まる(ロックイン)**状態になります。
この角度以降では、腱の遊び(slack)がなくなり、筋の張力が高まるため、内旋制動と関節安定化作用が増大します。
つまり、膝窩筋は屈曲角度によって「可動性 → 安定性」へと役割をシフトさせる筋といえます。
この特性は、膝関節屈曲中の軸制御や荷重位での動的安定化に大きく関与しています。
膝窩筋の機能解剖と動作特性
膝窩筋の走行をベクトル的に分解すると、主に以下の2つの作用が確認されます。
- 下腿内旋作用
膝屈曲初期で働き、下腿の外旋を制動します。
膝外側の「開き(varus)」や「外旋ズレ(外旋不安定症)」に抵抗することで、関節の回旋安定性を保ちます。 - 脛骨への軸圧作用(joint compression)
膝関節を後方から支えるように、脛骨を大腿骨に押し付ける力が生じます。
これにより、膝関節の**支点形成(pivot)**が強化され、荷重時の関節面安定性を確保します。
特に膝屈曲112°以上では、腱が腱溝にはまり込むため、これらの作用が効率よく発揮されます。
したがって、膝窩筋を効果的に収縮させるには、膝屈曲112°以上での下腿内旋運動が最も有効です。
臨床的意義:膝窩筋腱と外側安定性
膝窩筋は、単独での筋力発揮よりも、LCL・膝窩腓骨靭帯・外側半月板との連動で機能します。
とくに膝外側支持機構(posterolateral corner)の安定性に寄与しており、膝外反ストレスや外旋不安定を防ぎます。
✅ 臨床的なポイント
- 膝窩筋の過緊張
→ 外旋不安定症・knee in toe out アライメントで高頻度。 - 膝窩筋腱の滑走障害
→ 腱溝内での摩擦や滑走不良により、膝窩部痛や「引っかかり感」を訴える。 - リハビリ上の工夫
→ 屈曲位(約120°)での軽い下腿内旋運動を用いて、筋収縮誘導と腱滑走改善を狙う。
これにより、膝窩筋の張力を過度に高めず、外側支持機構の協調的安定化を促すことができます。
まとめ
膝窩筋腱と膝窩筋腱溝は、膝屈曲角度に応じてその機能を変化させる動的構造です。
- 伸展位:自由度が高く滑走性重視
- 屈曲位(約112°以上):溝にはまり込み、安定性重視
この特性により、膝窩筋は膝外側支持機構の一翼を担い、LCLや外側半月板とともに回旋・外反・過伸展を制動します。
理学療法においては、膝窩筋を「深層安定化筋」として捉え、
屈曲角度や滑走機能を意識した運動療法を設計することが、膝外側痛や不安定症の改善に直結します。