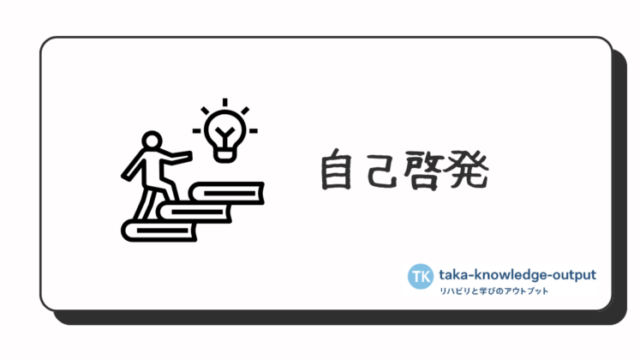『数字のトリック?「需給ギャップ」が隠す日本経済の真実』

計算できないはずの数字
経済ニュースを見ていると、「需給ギャップ」という言葉を耳にすることがある。 これは一国の経済における「供給能力」と「総需要」の差を示す指標である。 教科書的な説明では、需要が供給を上回ればインフレギャップ、下回ればデフレギャップとなるとされている。 しかし、ここで一つ、根本的な疑問を投げかけたい。 実は本来の意味において、インフレギャップという数値は計算できないはずのものなのだ。
どういうことか、シンプルな例で考えてみよう。 ある企業の供給能力、つまり1日に生産できる限界が90個だったとする。 それに対し、お客さんが「100個買いたい」と押し寄せたとする。 この場合、需要は100個だが、実際に売れるのはいくつだろうか。 当然、生産能力の限界である90個である。 ない袖は振れないし、作れない商品は売れない。 つまり、現実の取引量(名目GDP)が供給能力(潜在GDP)を上回ることは、物理的にあり得ないのである。 したがって、経済が過熱しているインフレギャップの状態であっても、計算上の需給ギャップは常に「ゼロ」になるのが論理的な帰結であるはずだ。
これに対し、デフレギャップの計算は容易である。 供給能力が100個あるのに、需要が90個しかなければ、売れ残りの10個がそのままギャップとなるからだ。 しかし、現実の統計データを見ると、なぜか「プラスの需給ギャップ(インフレギャップ)」が表示されていることがある。 生産不可能なはずの商品が買われていることになっているこの奇妙な現象は、一体なぜ起きるのだろうか。
「最大」から「平均」へのすり替え
そのからくりは、基準となる「供給能力(潜在GDP)」の定義にある。 私たちが普通「供給能力」と聞いてイメージするのは、工場や機械をフル稼働させ、労働者が最大限働いた時の「最大値」だろう。 これを経済学では「最大概念の潜在GDP」と呼ぶ。 この定義を採用するならば、前述の通り、現実の生産量が能力を上回ることはあり得ない。
ところが、日本の内閣府や日本銀行が採用している計算方法はこれとは異なる。 彼らは、過去の生産活動の平均値を基準とする「平均概念の潜在GDP」を使用しているのである。 わかりやすく言えば、テストの点数で「100点満点」を基準にするのではなく、「過去の平均点」を基準にしているようなものだ。 平均を基準にすれば、少し頑張って平均以上の点数を取れば「プラス」と判定される。 これと同様に、本来の最大能力には届いていなくても、過去の不況期の平均より少しマシであれば「インフレギャップ(需要超過)」として計算されてしまうのである。
統計変更が招いたデフレの長期化
この定義の変更が行われたのは2001年、当時の経済財政担当大臣であった竹中平蔵氏の時代にさかのぼる。 それまで「最大概念」で計算されていた潜在GDPが、「平均概念」へと書き換えられたのだ。 この変更がもたらした影響は計り知れない。
「平均概念」を使うことで、供給能力のハードルが低く設定されてしまう。 その結果、実際には深刻な需要不足(デフレギャップ)に陥っているにもかかわらず、統計上はそのギャップが小さく見えてしまうのだ。 「数字上はそこまで悪くない」という誤った安心感が生まれれば、当然、政府が行うべき景気対策の規模も縮小される。 十分な財政出動が行われず、需要不足が放置される。 日本でデフレがこれほどまでに長期化した背景には、この統計上の「過小評価」という問題が、ボディブローのように効いていたといえるだろう。 私たちが目にする経済指標、その数字の裏にある定義を疑う視点を持つことが、経済の本質を見抜く鍵となるのである。