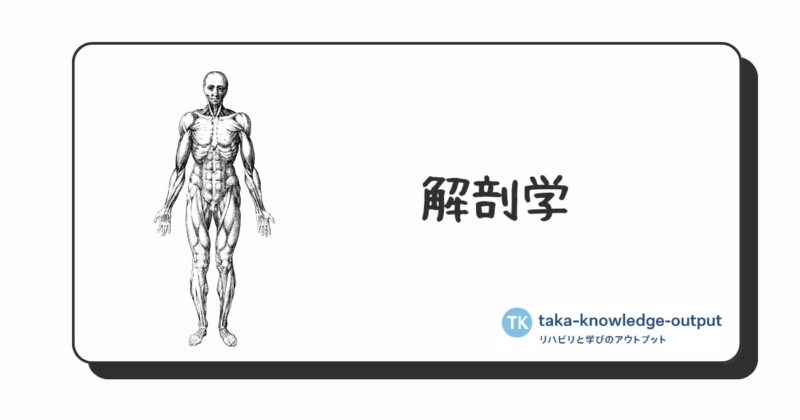TKAにおける関節内進入法の違いと理学療法への影響|大腿四頭筋侵襲の評価と屈曲制限の理解

TKAにおける関節内進入法の違いと理学療法への影響
大腿四頭筋への侵襲と可動域制限の関係を理解する
人工膝関節置換術(Total Knee Arthroplasty:TKA)において、関節内進入法(アプローチ)の選択は術後の疼痛・可動域・筋機能回復に大きく影響します。
特に、大腿四頭筋への侵襲の程度が術後早期の屈曲可動域制限や筋過緊張に関与するため、理学療法士は手術記録を確認し、進入法を把握した上でリハビリを設計する必要があります。
ここでは代表的な4つの進入法について、手術手技・特徴・リハビリへの影響を整理します。
1. Medial Parapatellar Approach(内側傍膝蓋アプローチ)
【概要】
TKAで最も一般的に用いられるアプローチです。
近位では大腿四頭筋腱と内側広筋の間を切離し、遠位では膝蓋腱付着部内側まで縦切して関節を展開します。
【特徴】
- 視野が広く、正確な骨切り・インプラント設置が容易
- しかし、大腿四頭筋腱への侵襲が比較的大きい
- 膝蓋骨の外側偏位や膝蓋大腿関節アライメント異常を生じやすい
【理学療法のポイント】
術後早期では**膝伸展時の疼痛や筋緊張亢進(quadriceps spasm)**が生じやすく、
屈曲訓練の際に「痛み→筋収縮→屈曲制限」という悪循環が起きやすいです。
- 他動屈曲は過度な牽引を避け、疼痛閾値内で実施
- 膝蓋骨の**モビライゼーション(特に内方・上方)**を早期から導入
- 大腿四頭筋の収縮-弛緩トレーニングを併用して過緊張を抑制
2. Subvastus Approach(内側広筋下アプローチ)
【概要】
膝蓋骨内側中央から内側広筋下縁に沿って剥離し、筋を切離せずに上外側へ牽引して展開します。
【特徴】
- 大腿四頭筋への侵襲が最も少ない
- 膝伸展機構が温存され、術後の疼痛・筋力低下が軽度
- ただし、術野が狭く手技難易度が高いため、重度変形例には不向き
【理学療法のポイント】
筋線維切離がないため、早期から膝伸展・屈曲訓練を積極的に導入可能です。
術後の膝伸展筋力の回復も早い傾向があります。
- 歩行訓練・階段昇降動作の導入が比較的早期に可能
- ただし、深屈曲位での疼痛が出る場合は、滑膜や内側支持機構の緊張を考慮して調整
3. Midvastus Approach(内側広筋分割アプローチ)
【概要】
膝蓋骨内側中央付近から、内側広筋線維の走行に沿って部分的に切離して展開します。
medial parapatellar approachとsubvastusの中間的な位置づけです。
【特徴】
- 大腿四頭筋侵襲が軽減され、伸展機構の温存が可能
- 術野の確保もしやすく、視野と侵襲のバランスが良い
- ただし、筋切離部の癒着が起こると屈曲制限が残存することも
【理学療法のポイント】
midvastusでは屈曲時に筋切離部の滑走不全や瘢痕性拘縮が生じやすいため、
- 屈伸可動域訓練とともに筋滑走の促進(マッサージ・温熱併用)
- 大腿四頭筋遠心性収縮トレーニングによる疼痛軽減と安定化
が有効です。
4. Lateral Approach(外側アプローチ)
【概要】
**重度外反膝(valgus knee)**に対して適応される特殊アプローチです。
外側支持機構を剥離し、内側の剥離を最小限に展開します。
【特徴】
- 外側構造(外側支帯・腸脛靭帯)のリリースが容易
- 内側組織への侵襲を抑えられる
- ただし、膝蓋骨を内側へ反転(eversion)しにくいという制限あり
【理学療法のポイント】
外側組織の剥離により、膝蓋骨追従性の変化や外側滑膜の緊張が生じることがあります。
- **膝蓋骨モビライゼーション(外方・回旋方向)**を重点的に実施
- 外側ハムストリング・腸脛靭帯の柔軟性を維持
- 外反膝特有の荷重偏位を考慮し、内側荷重誘導訓練を行う
まとめ:進入法の違いを理解して“屈曲制限の原因”を見極める
TKA後の可動域制限や疼痛の背景には、関節内進入法による筋・支持組織への侵襲パターンの違いが深く関与しています。
| アプローチ | 大腿四頭筋侵襲 | 視野 | 屈曲制限リスク | 特徴的な注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Medial Parapatellar | 高い | 広い | 高 | 大腿四頭筋緊張、膝蓋骨偏位 |
| Subvastus | 低い | 狭い | 低 | 早期筋機能回復 |
| Midvastus | 中等度 | 中等度 | 中 | 筋滑走障害、癒着 |
| Lateral | 症例限定 | 限定的 | 可変 | 外側組織の柔軟性低下 |
理学療法士は、術後の屈曲制限や疼痛を「リハビリの努力不足」と捉えず、
**「どの進入法で、どの筋が、どのように侵襲を受けたか」**を軸に評価を行うことが、
再現性の高い回復支援につながります。