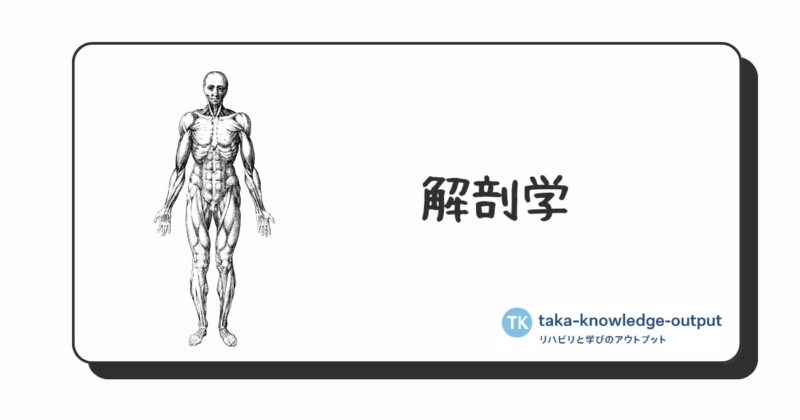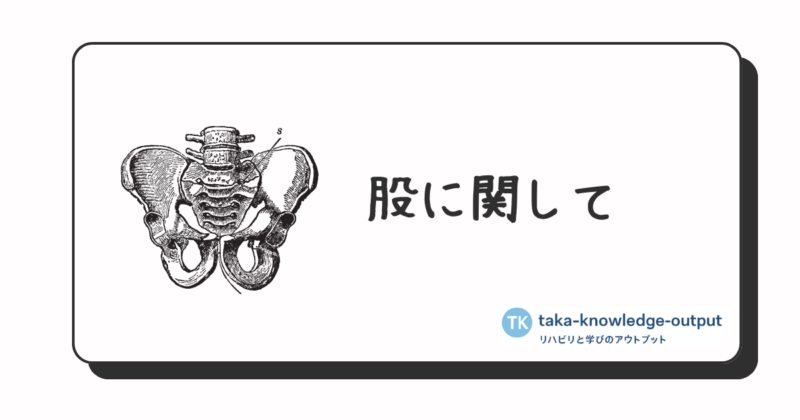膝の痛みと炎症のカギを握る「膝蓋下脂肪体(IFP)」とは?最新研究で見えた変形性膝関節症との関係

膝の中にある「知られざる臓器」―膝蓋下脂肪体(IFP)
変形性膝関節症(KOA)は、中高年を中心に世界中で患者数が増え続けている病気です。関節の軟骨がすり減ることで痛みや可動域制限が起こる、と理解されることが多いですが、実は「膝蓋下脂肪体(Infrapatellar Fat Pad, IFP)」という膝の中の脂肪組織も大きな役割を果たしていることが最新研究でわかってきました。
IFPは、膝のお皿(膝蓋骨)の下、脛骨の前方に位置する脂肪組織で、クッションのように衝撃を吸収し、膝の安定性を支えています。しかし、この脂肪体が炎症を起こすと線維化(硬くなること)が進み、痛みや関節機能の悪化につながる可能性があります。
最新研究が明らかにしたIFPの「細胞マップ」
カナダの研究チームが行った最新の解析では、膝蓋下脂肪体を対象に、最先端の「シングルセルRNA解析」と「空間トランスクリプトミクス」という手法を用いて、どんな細胞がどのように働いているのかを詳しく調べました。
その結果、以下の主要な細胞が確認されました。
- 線維芽細胞(Fibroblasts):全体の約44%を占め、炎症や線維化に深く関わる
- マクロファージ(Macrophages):約19%、炎症反応や組織修復を担う
- 脂肪細胞(Adipocytes):約16%、代謝や炎症因子の分泌に関与
- 血管内皮細胞(Endothelial cells):約12%、血管形成や炎症制御に関与
さらに線維芽細胞の中には「前駆細胞(未熟な状態)」と「分化した細胞」があり、炎症や線維化の進行に伴ってその割合や働きが変わっていくことが示されました。
肥満と性差がIFPに与える影響
この研究では、患者の性別や肥満度(BMI)によってもIFPの働きに違いが出ることが明らかになりました。
- **肥満(BMI 30以上)**の患者では、脂質代謝や炎症に関わる遺伝子の働きが変化しており、炎症や痛みを悪化させる可能性がある。
- 女性では、関節の潤滑を助ける「PRG4」という遺伝子の働きが強く、一方で肥満患者ではその働きが弱まることがわかりました。
つまり、肥満や性差によってもIFPの炎症や代謝バランスが変化し、膝の痛みや関節症の進行に影響しているのです。
なぜこの研究が重要なのか?
これまでの膝関節症の研究は「軟骨」や「骨」に注目が集まりがちでした。しかし、この研究によって 「膝蓋下脂肪体」という膝の中の脂肪組織が、炎症や痛みに深く関与している ことが明確になりました。
今後、IFPをターゲットにした治療法(例:抗炎症療法や線維化抑制、代謝改善)が開発されれば、膝の痛みを和らげ、進行を防ぐ新しいアプローチにつながるかもしれません。
まとめ
- 膝蓋下脂肪体(IFP)は、膝関節内で炎症や痛みに関与する重要な組織。
- 最新研究で、IFPの細胞構成や働きが「遺伝子レベル」で解明された。
- 肥満や性差がIFPの炎症や代謝に影響を与え、膝関節症の進行に関わる可能性がある。
- 将来的に、IFPをターゲットにした新しい治療法が登場するかもしれない。
膝の痛みと向き合ううえで、「軟骨」だけでなく「脂肪体」にも注目することが重要になりそうです。