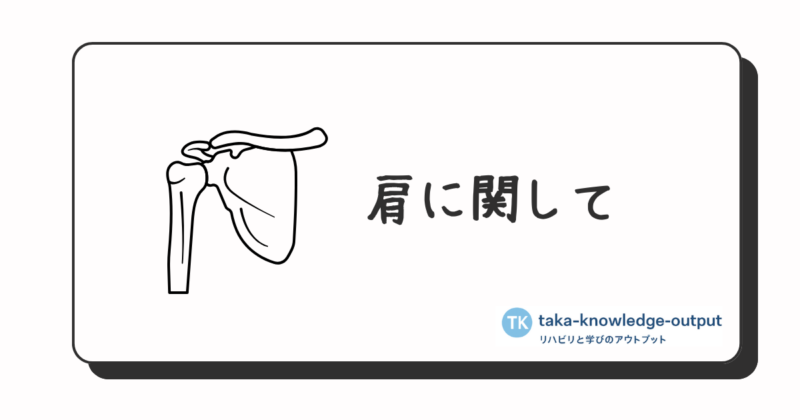拘縮をどう捉えるか:可動域制限と疼痛改善のための臨床的視点

拘縮は臨床でなぜ重要か
運動器疾患の臨床では、セラピストが対応する多くの症状に「拘縮」が深く関わっています。拘縮を改善できるかどうかは、関節可動域(ROM)の拡大だけでなく、疼痛の軽減や動作改善にも直結します。
一般的に「拘縮=関節が固まった状態」と理解されがちですが、実際にはより複雑です。拘縮は以下のような状態を含む総称と捉えることが適切です。
- 筋が攣縮・短縮して硬くなっている状態
- 靭帯や関節包の滑走性が低下している状態
- 脂肪体などの軟部組織の柔軟性が失われている状態
つまり、拘縮とは単なる「関節の硬さ」ではなく、複数の組織の機能低下が絡み合った結果として現れる症状なのです。
拘縮と疼痛の関係
拘縮は可動域制限と密接に関係しますが、それだけではありません。多くの場合、疼痛の増悪因子にもなります。
臨床的に、拘縮が改善すると腰痛などが緩和するケースは珍しくありません。これは拘縮が疼痛を誘発する仕組みと関係しています。
1. 圧刺激による疼痛
軟部組織に強い圧が加わると、ポリモーダル受容器が刺激されて痛みが生じます。臨床では、圧痛、伸張痛、収縮痛といった形で表れます。
2. 摩擦刺激による疼痛
皮膚・筋膜・靭帯・滑膜・脂肪体などの組織間が硬くなると、滑走性が低下します。この状態で運動が繰り返されると、摩擦刺激が増加し、侵害受容器が反応して疼痛が生じます。
拘縮改善の基本戦略
拘縮を改善するためには、伸長性・滑走性・柔軟性が低下した組織を特定し、アプローチすることが重要です。単に可動域を広げるだけでは、翌日まで効果を維持したり、疼痛を改善することは難しいでしょう。
そのため、評価の段階で「どの組織が原因となっているか」を見極めることが必要です。
拘縮の組織別分類と特徴
拘縮を理解し、原因組織を見つけるためには、各軟部組織の特徴を知る必要があります。代表的な4種類を整理します。
1. 皮膚性拘縮
- 特徴:皮膚や皮下組織の滑走性・伸長性が低下
- 評価のポイント:皮膚つまみテストや皮膚の動きの制限を観察
2. 筋・筋膜性拘縮
- 特徴:筋の攣縮・短縮、筋膜癒着によって可動域制限が生じる
- 評価のポイント:ストレッチ痛や筋硬度計測、触診での抵抗感
3. 靭帯・関節包拘縮
- 特徴:周囲組織との滑走障害、あるいは靭帯・関節包自体の伸長性低下
- 評価のポイント:関節包パターンの有無、ストレステストでの抵抗
4. 脂肪体拘縮
- 特徴:脂肪体の柔軟性低下や変形不全、周囲組織との滑走障害
- 評価のポイント:関節運動時の挟み込み感、局所の圧痛
臨床への応用
臨床家に求められるのは、可動域制限そのものを操作するのではなく、原因組織を見極めたうえでアプローチを選択することです。
- 皮膚性拘縮 → 皮膚モビライゼーション
- 筋・筋膜性拘縮 → 筋膜リリース、ストレッチング
- 靭帯・関節包拘縮 → 関節モビライゼーション
- 脂肪体拘縮 → 圧迫・挟み込みを回避する運動療法
このように、原因組織に即した治療を行うことで、関節可動域だけでなく疼痛や動作の質の改善につながります。
まとめ
- 拘縮は「関節が固まること」ではなく、皮膚・筋膜・靭帯・脂肪体などの柔軟性低下や滑走障害の総称である。
- 拘縮は疼痛(圧痛・伸張痛・収縮痛、摩擦痛)を引き起こす重要因子である。
- 改善には、原因組織を評価から見極め、伸長性・滑走性・柔軟性を回復させることが必要。
- 臨床では「拘縮の種類ごとの特徴」を理解して介入を選択することが鍵となる。
拘縮を正しく捉え、適切に改善していくことが、可動域拡大だけでなく疼痛緩和や機能改善にもつながるのです。