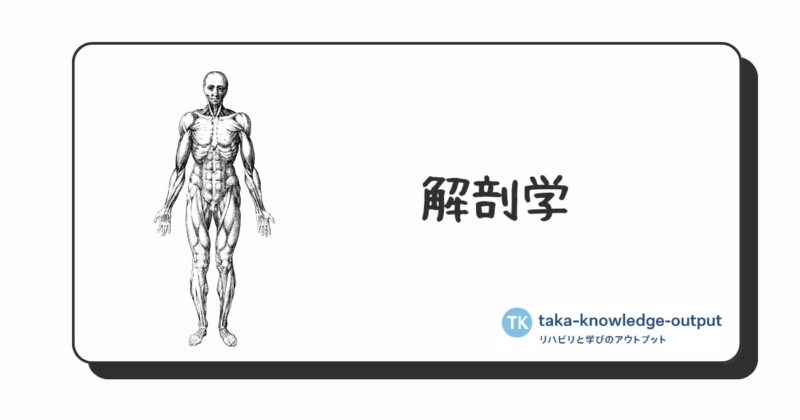筋緊張亢進と慢性痛の関係:圧痛・伸張痛を改善する臨床アプローチ

筋緊張亢進と慢性痛のつながり
臨床現場において、筋緊張が亢進している部位に負荷が加わることで疼痛が生じる場面は少なくありません。特に長期にわたる筋緊張の持続は、単なる「こわばり」ではなく、組織変性を引き起こす大きな要因となります。
その背景には以下のような機序があります。
- 血管の攣縮
筋緊張が続くと血管が圧迫され、攣縮が生じます。 - 虚血による組織変性
血流不足は筋組織の虚血を招き、代謝障害や組織の変性を引き起こします。 - 発痛関連物質による感作
虚血環境では乳酸やブラジキニン、プロスタグランジンなどの発痛関連物質が蓄積し、知覚神経を感作します。
こうした一連の流れによって、筋緊張が亢進した部位では圧痛や伸張時の痛みが出現しやすくなるのです。
筋緊張亢進に伴う疼痛への臨床的対応
筋緊張が強い部位に伸張痛を有するケースでは、単にストレッチを行うだけでは不十分です。重要なのは、
- 筋緊張を緩和させること
- 筋の伸張性を改善すること
この2つを同時に狙った介入です。
臨床で活用しやすい方法として、
- 筋の短軸滑走
- 収縮と短縮からの伸長
の2つを紹介します。
筋の短軸滑走
方法
治療者の指を隣接する2つの筋間に差し込み、筋同士を「引きはがす」ように操作します。単に離開するだけでなく、離開 → 戻す → 再び離開というリズミカルな操作を繰り返すことがポイントです。
目的と効果
この操作により、筋間の線維組織が短軸方向に伸び縮みを繰り返し、組織間の伸縮性が改善されます。その結果、筋緊張が緩和すると同時に、筋の伸張性向上も期待できます。
収縮と短縮からの伸長
方法
- 伸張性を改善したい筋をまず伸張する。
- その筋に自動収縮を行わせる。
- 短縮位まで収縮させた後、治療者がさらに徒手的にわずかに短縮させる。
目的と効果
筋は収縮後に反回抑制が働きます。また、短縮操作によって拮抗筋が防御的に収縮し、相反抑制が加わります。これらの作用が組み合わさることで、対象筋は弛緩せざるを得ない状態となり、筋緊張の効果的な抑制が得られます。
臨床応用のポイント
両手技はいずれも「筋緊張の抑制」と「伸張性の改善」を同時に達成できる点で有用です。慢性痛の背景には、単なる力学的負荷だけでなく、虚血・感作・組織変性といった生理学的プロセスが絡んでいます。そのため、ストレッチや筋力強化のみでは不十分であり、筋の状態に応じた適切な介入が必要となります。
さらに、これらのアプローチは徒手療法だけでなく、患者自身のセルフエクササイズへと応用可能です。例えば、軽度の短軸滑走を自己マッサージとして行ったり、収縮と短縮からの伸長を自主トレーニングに組み込むことで、臨床外でも効果を持続させることができます。
まとめ
- 筋緊張亢進は血管攣縮・虚血・感作を経て慢性痛を誘発する。
- 圧痛や伸張痛の背景には、筋緊張が大きく関与している。
- 臨床的には「筋の短軸滑走」と「収縮と短縮からの伸長」が有効な手段となる。
慢性痛を訴える患者に対しては、単なる筋ストレッチだけではなく、筋緊張の解消と伸張性の改善を両立させるアプローチを選択することが重要です。