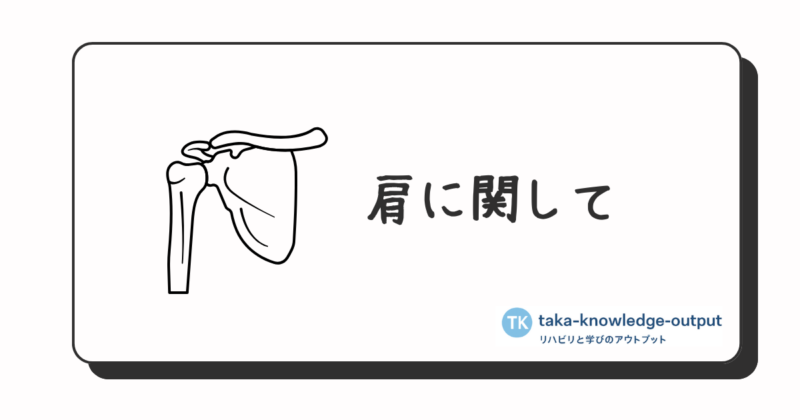拘縮肩とは
肩関節に可動域制限を有した状態を総称して「拘縮肩」と呼びます。大きく分けると:
- 一次性拘縮肩(凍結肩):原因不明に発症する一時的拘縮
- 二次性拘縮肩:外傷や術後など明らかな障害に続発する拘縮
臨床では痛み・関節可動域制限・筋力低下・感覚異常などの所見が認められますが、その中でも末梢神経症状への対応を優先することで病態把握が容易になる点が重要です。
肩甲上神経の解剖
肩甲上神経はC5・6神経根に由来し、腕神経叢から分岐します。その後:
- 肩甲切痕と棘下切痕を通過
- 肩甲上動静脈と並走
- 内側肩甲下枝・棘上筋枝・外側肩甲下枝を分岐
- 最終的に後肩甲上腕枝・棘下筋枝に分枝
肩甲上神経は棘上筋と棘下筋を支配するため、神経障害は腱板機能や肩関節安定性に直結します。
腋窩神経の解剖
腋窩神経もC5・6神経根に由来し、腕神経叢後神経束から分岐します。
- 肩甲骨外側で前枝と後枝に分かれる
- 前枝:上腕骨と上腕三頭筋長頭の間を通過 → 三角筋前部・中部を支配
- 後枝:小円筋枝・三角筋後部枝・上腕外側皮神経枝へ分枝
また、大円筋や肩甲下筋は下肩甲下神経による支配を受けますが、腋窩神経からの枝との関連も重要です。
侵害刺激と筋スパズム
拘縮肩症例の多くでは、痛みに加えて侵害受容性反射に基づく持続的な筋攣縮が腱板筋群を中心に認められます。
例として肩甲上神経を挙げると:
- 炎症や外傷などによる肩関節内の侵害刺激
- 神経走行部での圧迫や障害 → これらが脊髄反射を介して、肩甲上神経支配筋(棘上筋・棘下筋)の攣縮を引き起こします。
腱板損傷や断裂を契機に炎症が持続し、末梢神経を中心とした攣縮が長期化すると、
- 神経活動性の低下
- 機械的刺激による疼痛の再発
- さらに関節拘縮へ進行 といった悪循環が形成されます。
理学療法での臨床的示唆
- 末梢神経症状を優先評価
可動域制限だけでなく、神経支配筋の攣縮・萎縮や感覚異常の有無を確認する。
- 侵害受容反射の介入
筋スパズムの改善を目的とした徒手療法や運動療法を行い、神経の活動性を回復させる。
- 関節拘縮の進行予防
ストレッチやモビライゼーションだけでなく、肩甲帯全体の動きを整えることが重要。
まとめ
- 拘縮肩は一次性・二次性に分けられるが、末梢神経症状への理解が病態把握の鍵となる。
- 肩甲上神経・腋窩神経の解剖学的走行を把握することが臨床に直結する。
- 侵害受容反射に伴う筋攣縮は、疼痛・拘縮進行の悪循環を生むため早期介入が必要。
肩関節拘縮への理学療法では、単なるROM改善ではなく、神経・筋・関節の統合的評価と介入が求められます。
ABOUT ME

理学療法士として臨床に携わりながら、リハビリ・運動学・生理学を中心に学びを整理し発信しています。心理学や自己啓発、読書からの気づきも取り入れ、専門職だけでなく一般の方にも役立つ知識を届けることを目指しています。