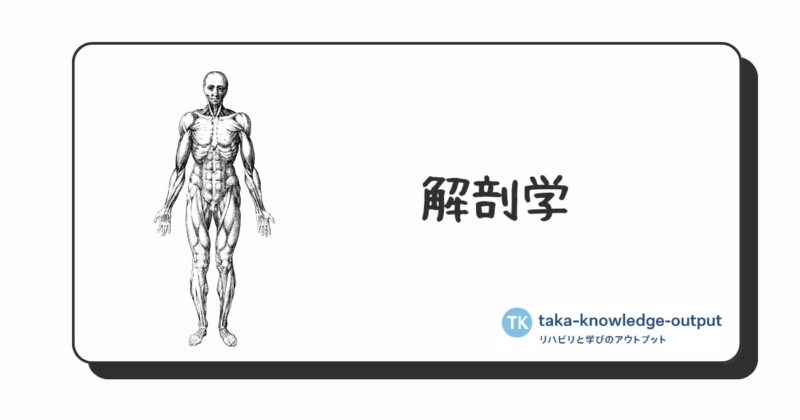筋膜の4つの分類
筋膜(fascia)は、従来の解剖学では「筋や骨を包む補助的な組織」として軽視されがちでした。
しかし近年では、身体の連続性を保つ重要な構造として再評価されています。筋膜は大きく以下の4つに分類されます。
- 浅筋膜(superficial fascia / pannicular fascia)
- 皮下組織に相当し、皮膚のすぐ下に広がる
- 脂肪細胞を多く含む疎性結合組織
- 体全体を覆う「柔らかい包装材」として機能
- 深筋膜(deep fascia / investing fascia)
- 全身の筋骨格系を覆う一続きの層
- 骨格筋を包む筋外膜(epimysium)、腱を包む腱膜(peritenon)、靭帯や骨膜(periosteum)と連続
- 部位により 軸筋膜(axial fascia) と 体肢筋膜(appendicular fascia) に分けられる
- 髄膜(meninges)
- 臓器を包む膜
胸腰筋膜 ― 深筋膜の代表例
深筋膜の中でも、臨床で特に注目されるのが 胸腰筋膜(thoracolumbar fascia) です。
- 構造:多層性(後葉・中葉・前葉の3層)を持つ
- 範囲:
- 頸部では薄く「項筋膜」として固有背筋を覆う
- 胸部では肋骨角に付着し、背筋を覆う
- 腰部では肋骨がないため、固有背筋を「鞘状」に包み込み、さらに腰方形筋まで覆う
- 特徴:交織密性結合組織であり、多方向の張力に適応する
👉 胸腰筋膜は、体幹の安定性・運動連鎖・腰痛の病態と深く関わる部位として臨床上も重要です。
筋膜が見落とされてきた理由
従来の解剖学分類では、運動器系は以下のように分けられていました。
この枠組みでは「筋膜」は独立した系統として扱われず、骨・筋・靭帯をつなぐ結合組織として十分に注目されてきませんでした。
しかし実際には、筋膜は 身体を一つのネットワークとして機能させる鍵であり、疼痛や可動域制限、姿勢制御に深く関与します。
まとめ
- 筋膜は 浅筋膜・深筋膜・髄膜・臓器膜 に分類される
- 深筋膜の中でも 胸腰筋膜 は体幹安定性に直結し、臨床的に重要
- 筋膜は「単なる補助組織」ではなく、身体全体をつなぎ、力と情報を伝えるネットワークである
👉 筋膜の理解は、筋膜リリース・運動療法・疼痛治療の基礎となります。
ABOUT ME

理学療法士として臨床に携わりながら、リハビリ・運動学・生理学を中心に学びを整理し発信しています。心理学や自己啓発、読書からの気づきも取り入れ、専門職だけでなく一般の方にも役立つ知識を届けることを目指しています。